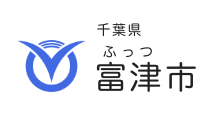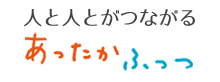あしあと
『あ』行
- 初版公開日:[2025年10月02日]
- 更新日:[2025年10月2日]
- ID:944
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あ
.jpg)
鶴岡のかっこ舞(市指定)
佐貫の鶴岡地区に伝わる「かっこ舞」は、毎年7月第一日曜日の浅間神社の祭礼で、雨ごいのために奉納されています。
市内に伝承される唯一の「かっこ舞」です。
鶴岡のかっこ舞については、市宝探訪(民族)をご覧ください。
い
.jpg)
金谷神社の大鏡鉄(県指定)
日本武尊が東征の時、船の舳にかけてきたとも伝えられている大鏡鉄は、金谷神社に「鉄尊様」として大事に納められ、海の安全や豊漁をもたらす「釜の蓋様」として信仰されています。直径160センチメートル、厚さ11センチメートル、重さ1.5トンの大鏡鉄は砂鉄を原料にして造られ、金谷の地にかつて高い技術を持った製鉄関連の民がいたことを伝えているようです。
金谷神社の大鏡鉄については、市宝探訪(工芸)をご覧ください。
う
.jpg)
関の姥石
関の姥石は、上部が窪んだ八角形をした大きな石で、環から関豊に通じる道路沿いにあります。地元では、この石は「関の姥さま」というお話で、姥さまの袂にあった石臼が落ちたものだと、伝わっています。
関には他にも、巨人伝説や巨石信仰をはじめ、いろいろな民間伝承があります。
姥石については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
え
.jpg)
海苔
富津市は県下でも有数の海苔の生産地です。江戸時代から養殖は始まりましたが、生産が安定したのは明治時代初期になります。
ノリヒビを移し変えることにより、海苔がたくさん採れる方法を開発した大堀村の平野武治郎は、海苔作りの功労者の一人です。
いまは、浅瀬にノリヒビをたてるのでなく、沖合いにベタ流しによる方法で生産しています。
お
.jpg)
薬王寺のオハツキイチョウ(県指定)
竹岡の薬王寺境内には、葉の先に実をつける珍しいイチョウの木があります。
「オハツキイチョウ」といい、およそ高さ18メートル、根回り3.1メートル、枝張り南北15メートル、東西14メートルもある大きな木です。
薬王寺のオハツキイチョウについては、市宝探訪(自然)をご覧ください。