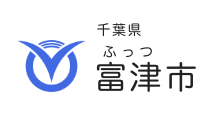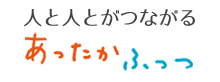あしあと
関尻大わらじ
- 初版公開日:[2025年02月07日]
- 更新日:[2025年2月7日]
- ID:3167
関尻大わらじ
関尻地区では、毎年、節分の日に部落の人たちで集まり、疫病神から地域を守るために、大わらじを編んで3カ所に吊るします。
なぜこのような大わらじが作られたかというと、昔、この付近で疫病が流行したときに、疫病神を自分の部落に入れないため「この部落にはこんな大きなわらじを履く大男がいるぞ」という意味で部落境の3カ所に大わらじを吊り下げました。
また、このわらじに添えてある木炭・杉の小枝・酒ダルには次のような意味があります。
- 木炭は、「私の部落では疫病は済み(炭)ました。」
- 杉の小枝は、「私の部落では疫病が過ぎ(杉)ました。」
- 酒ダルは、引き返していく疫病神のあとの祟りが恐いということからお酒でもてなし、新しいわらじを履いて帰っていただく。
さまざまな言い伝えがありますが、部落の方たちの間では、このように親から子へ代々引き継がれているそうです。
この動画では、大わらじの製作過程と、実際に吊るされる様子を紹介します。