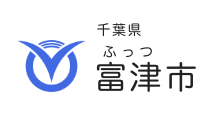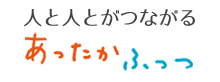あしあと
9月1日は『防災の日』
- 初版公開日:[2021年08月30日]
- 更新日:[2025年9月1日]
- ID:6853
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
『防災の日』
大正12年(1923年)9月1日に発生した関東大震災は、死者・行方不明者10万5千余人という大惨事になりました。
この震災を教訓として、一人ひとりの防災対策の重要性を広く国民に理解してもらうため、9月1日が『防災の日』と制定されました。
地震だけでなく、日本は台風、豪雨などの自然災害が発生しやすい国です。さまざまな災害に備え、日頃からの防災対策をしっかりしておきましょう。
今すぐできる「7つ」の備え
その1 災害被害を少なくする「自助」・「共助」
「災害はひとごと」と思っていませんか?
災害は、いつどこにやってくるかわかりません。
災害をくい止めることはできませんが、災害による被害は、私たちの日ごろの努力によって減らすことが可能です。
行政による「公助」はいうまでもありませんが、自分の身は自分で守る「自助」、地域や身近にいる人同士が助け合う「共助」こそが、災害による被害を少なくするための大きな力となります。
平時から、「自分でできること」、「家族でできること」、「ご近所と力を合わせてできること」などについて考え、いつくるかわからない災害に備えておくことが大切です。


その2 あなたのお宅やご近所は安全ですか??
防災ハザードマップ(ハザードマップ)
『防災ハザードマップ』は、大地震・津波・洪水などの自然災害が発生した場合の被害想定の範囲や、避難・救援活動に必要な情報が掲載されている地図です。
この機会に、家族みんなで『富津市Web版ハザードマップ』を確認しましょう。
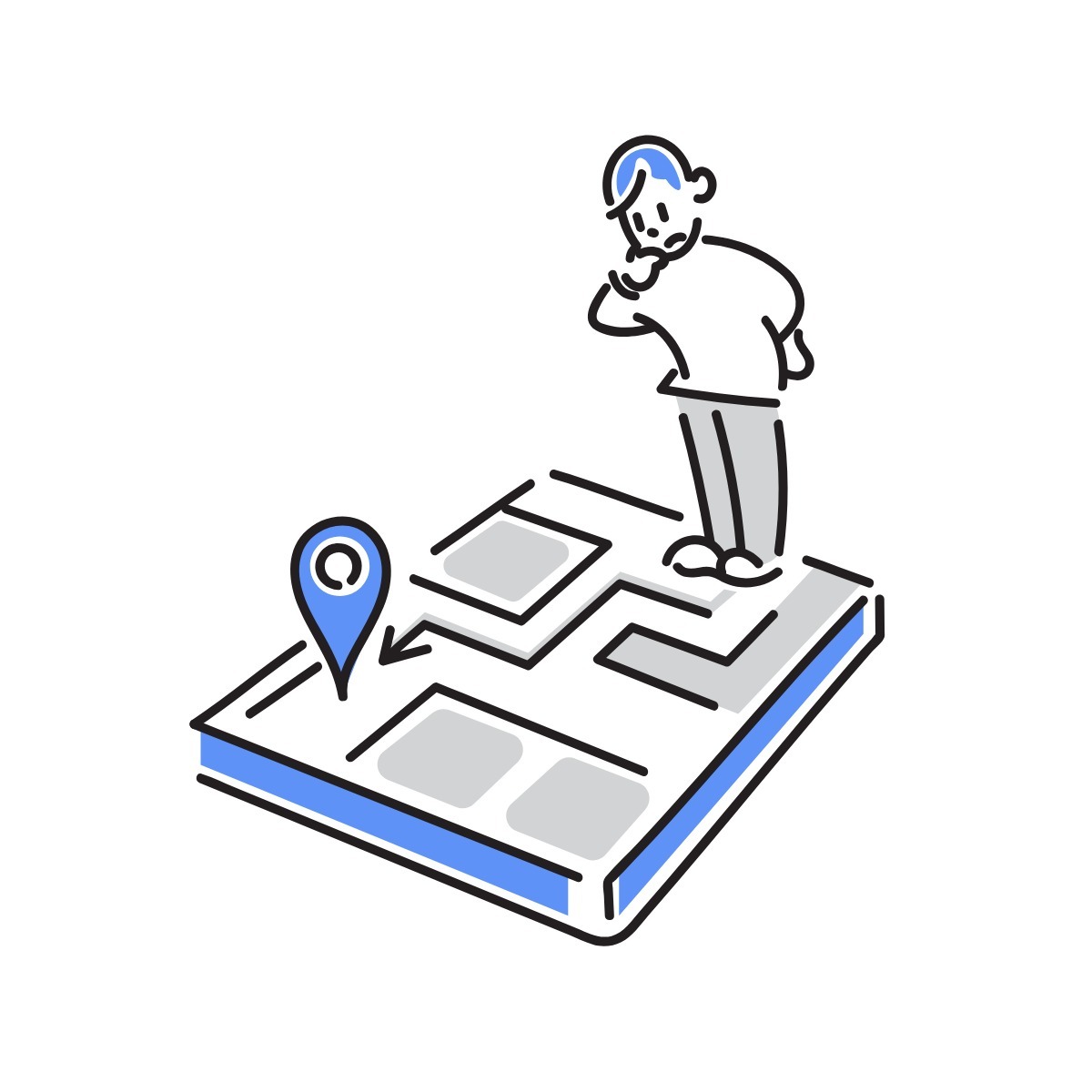
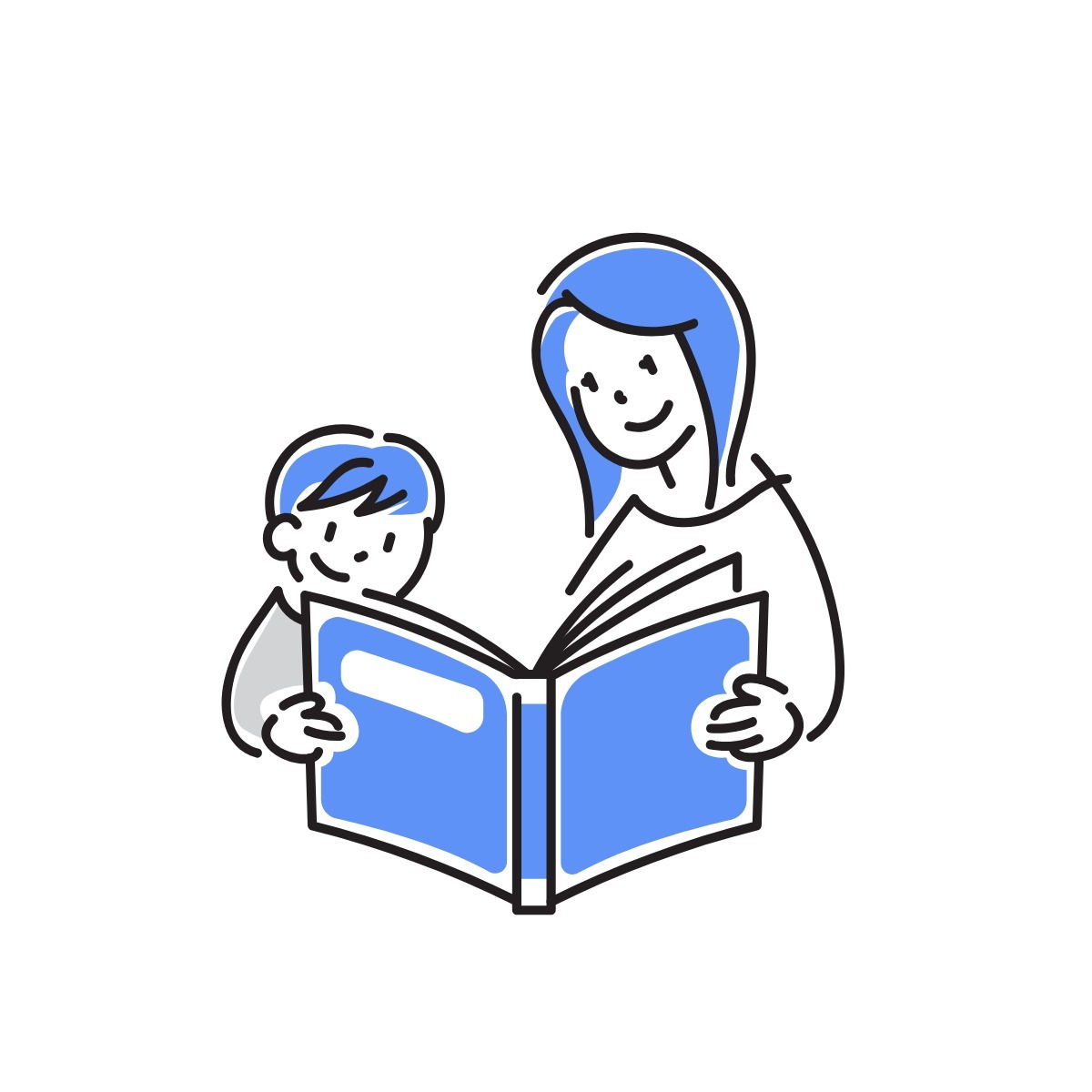
防災ハザードマップの活用方法 『ぼうさいまち歩き』
『ぼうさいまち歩き』とは、自分たちの住んでいるまちを探検して歩き、まちの中にある危険な場所を知り、まちの中の防災施設などを発見していくものです。
これらを通して地域の歴史を学び、防災への関心が高まり、『ぼうさいまち歩き』で発見したことを地図に書きこむことは、災害に対応するために何をすればよいかを考えるきっかけとなり、自主防災組織や家族単位で作成したマップは、災害時のマップとして活用できます。
この機会に、区や家庭で『わがまちの防災マップ』を作ってみましょう。


富津市では、『富津市出前講座』の制度を活用して自治会や自主防災組織が行う防災マップの作成を支援しています。
詳細は、『富津市出前講座』をご確認いただきお問い合わせください。
その3 あなたのお宅は 地震に耐えられますか?
あなたのお宅は、何年に建てられましたか?
昭和56(1981)年に、住宅の建物の強さを定める基準が大きく変わりました。
この年以降に建てられているかどうかが、自分の家の強さを知る一つの目安となります。 ※昭和56(1981)年以降が新耐震基準


住宅は、年月の経過ととも変化します。
点検・整備をこまめに行うことや、万が一の際にも補修や 再建の助けとなる地震保険などの経済的な手だてについても、家族で話し合っておきましょう。
詳細は、『わが家の耐震相談会(富津市建設経済部都市政策課)』を確認してください。
その4 災害から命を守る
災害の怖さを知ろう(地震・室内編)
近年、テレビや新聞、雑誌でさかんに防災や 減災の取り組みが紹介されています。
特に、ご家庭や暮らしの中でのひと工夫で実現できる 「家具の転倒・落下防止」については、さまざま なグッズやアイデアが紹介されています。
大地震のときには、多くの方が「家具類の転倒・落下」 によって負傷してしまうこともわかっていますが、実際に家具類の転倒防止対策を講じている人はわずか24.3%という調査結果があります。
※内閣府:「地震防災対策に関する特別世論調査」(平成19年)
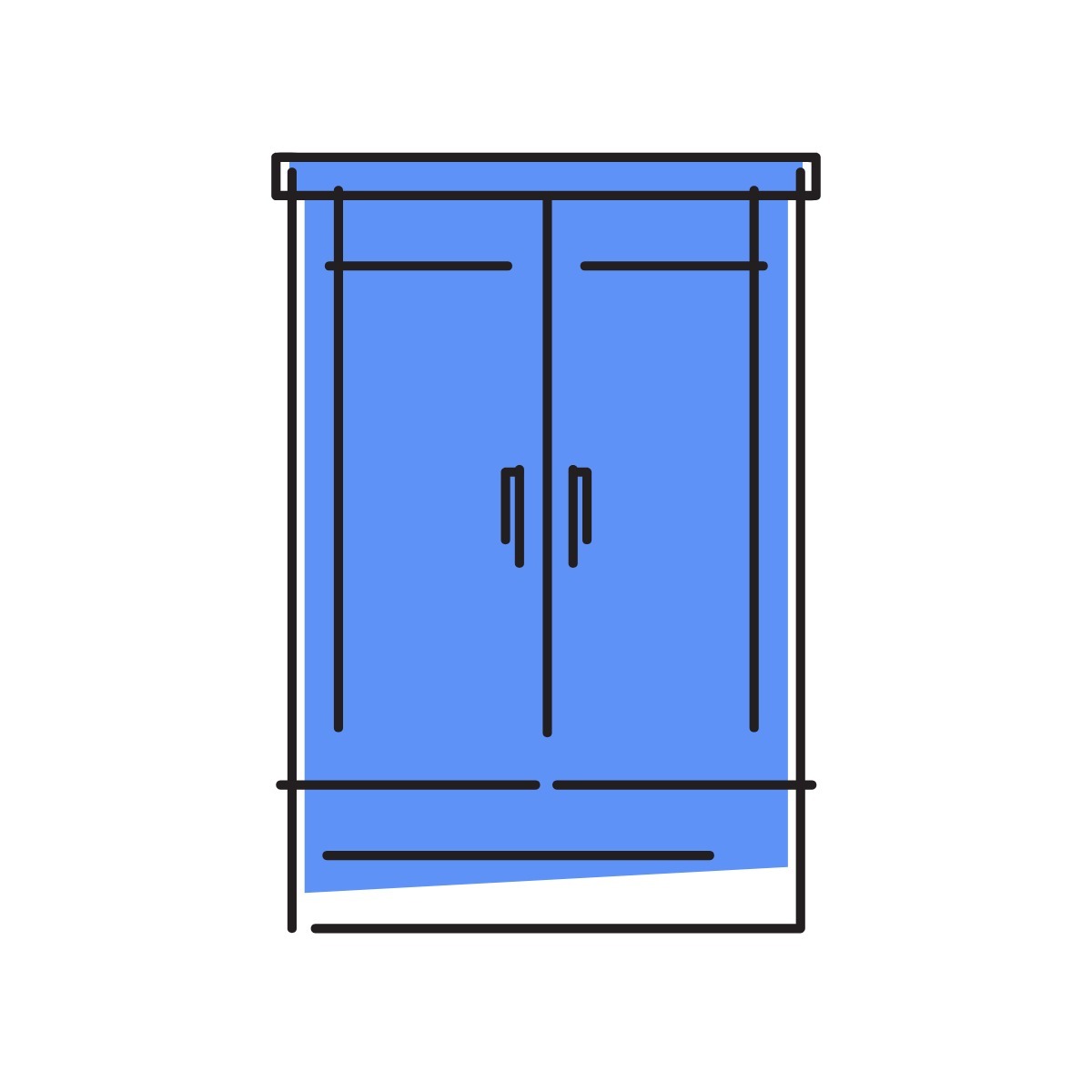

災害時において「家具類の転倒・落下」によって負傷する人の割合は高くなっています。
家具類の転倒・落下を防ぐ方法はいろいろとありますが、建物の構造やお部屋の状況に応じた手立てを行なうことが求められます。
少しの時間と工夫によって、あなた自身や大切なご家族を大ケガから守りましょう
●大地震では、テレビが飛び、タンスがあなたの上に倒れかかってきます!
阪神・淡路大震災でも、多くの方が倒れてきた家具の下敷きになって、尊い命を失ったり、大ケガをしたりしました。
また、多くの地震において室内でテレビや家具が散乱し、逃げ遅れた方々がいます。
●窓ガラスや食器は、鋭い破片を床一面に広げ、あなたの行く手をはばみます
食器棚から飛び出てきた食器や窓ガラスが室内に散乱します。
床一面が割れたガラス窓や割れた食器やグラスなどで覆われ、とても素足では歩ける状態ではありません。
スリッパやズック靴などをいつでも使えるように枕元へ置いておきましょう
●「生き残ってから」のことよりも、「生き残るため/死なないための努力」を先に行いましょう
『緊急地震速報』を見聞きしても、家の中に安全な場所がなければどうしようもありません。
家の中や職場など、まずは、身近な空間の安全点検と必要な対策が最優先です。
家具の固定や配置の見直しで「安全空間」を!
家庭内に「安全空間」をつくっておくことで、災害時に安心して暮らすことができます。
「大地震では、家具は必ず倒れるもの」と考えて、お部屋の総点検を行いましょう。
その際にチェック・実践すべき点は 次の5つです。まずはできる部分からはじめましょう。
〇家具は、倒れる向きを考えて配置しましょう
〇家具部屋を作りましょう(寝室や居間として使用しない)
〇作りつけの家具を使いましょう
〇寝室には家具を置かないようにしましょう
〇家具を置く場合は、固定することで転倒防止をはかりましょう(家具の固定方法にはいろいろありますが、正しいやり方で行わなければ効果は期待できません)
災害の怖さを知ろう(風水害編)
集中豪雨には、最新の気象情報の入手と日頃からの備えが大切です。
〇ラジオやテレビの気象情報に注意しましょう(事前に情報が入手できれば、早めの対策を講じることができます)
〇停電に備え、懐中電灯はすぐに使えるよう、部屋ごとに置いておきましょう
〇デマやフェイクユニュースにまどわされないよう、正しい情報の入手先を決めておきましょう
〇河川や用水路、田んぼや低地などの状況を確認しに行くことは控えましょう(水の状況は急変しますので、非常に危険です)
〇日頃から「避難場所」や「避難経路」を確認しておくことが重要です(ハザードマップで調べたり、ホームページなどで確認しておきましょう)
〇自分が住む地域が、過去に水害を経験した土地かどうか、日頃から調べておきましょう


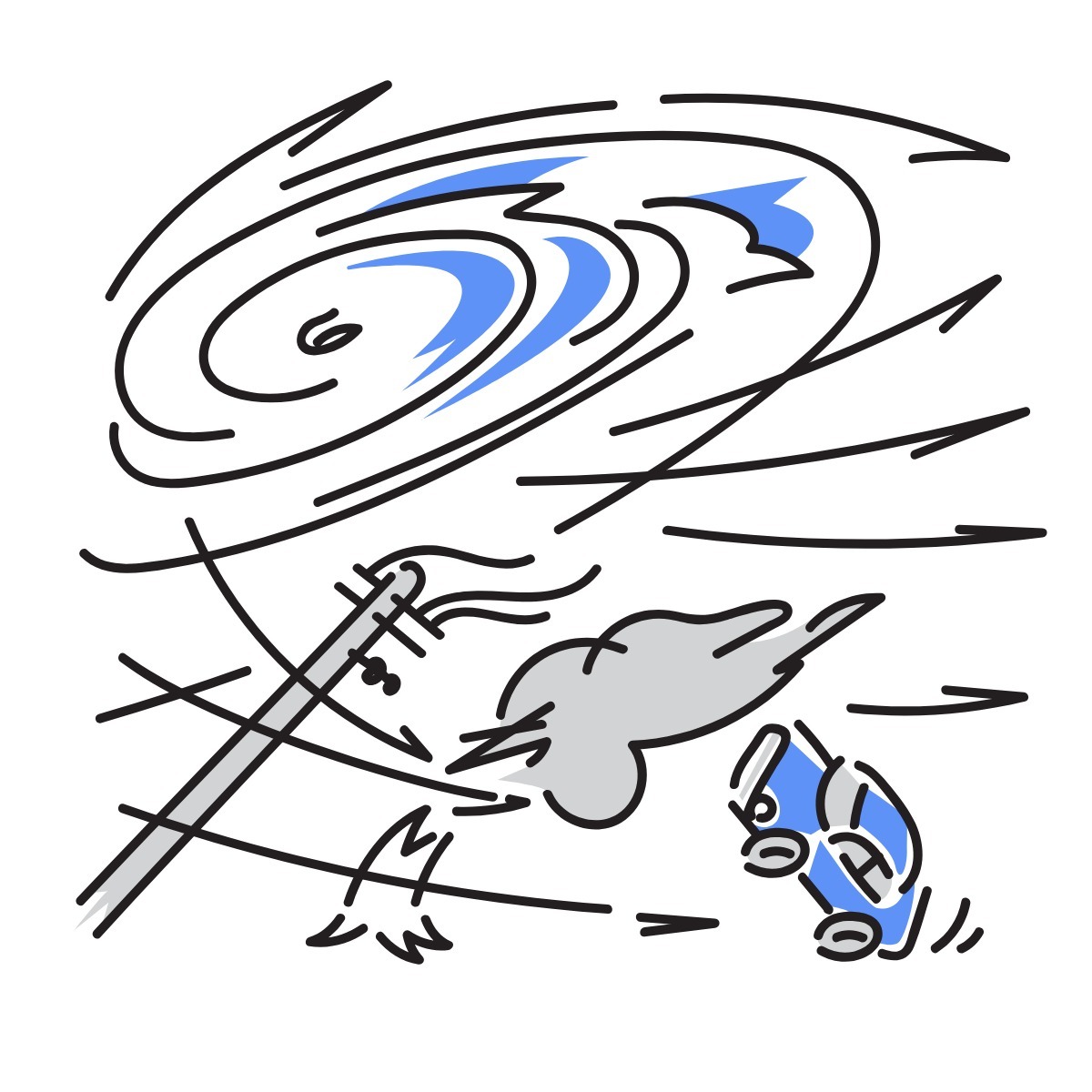
その5 日ごろから準備しておきたいもの
『非常用持ち出し袋』のほかにも、さまざまな「備え」が、あなたの被災生活を支えます。
重要なことは、無意識に持って歩けるような気軽さです。大きさ・軽さもさることながら、サイフに入る、キーホルダーに付く、バッグや衣服のポケットに入れっぱなしにできるところがポイントです。
自分に関する情報
身元や連絡先を記したカード・病院の診察券、病名、処方薬を書いたメモ
状況を把握するためのもの
ポケットラジオ・スマートフォン用のモバイルバッテリー・メモ帳や筆記具
閉じ込められた時のためのもの
笛(ホイッスル)・水筒などで水分や飲料・チョコレート等の補食・火災時に口を覆うためのハンカチ
防災のために特別なものを用意するのではなく、できるだけ、普段の生活の中に組み込んで、平時に 無意識に更新されるものでまかないましょう。
安価でどこでも入手しやすいものでないと、定期的に更新したり分散して置くことができません。
例えば、ティッシュやトイレットペーパー、ラップ、アルミホイル、大型ゴミ袋、水のペットボトル などは、ある程度の量を蓄え、順々に古い方から使い、日常生活で買い足していきましょう。
速やかな避難のためのもの
紐なしのズック靴・LEDライト・革手袋・レインコート
なければ困るもの
常備薬・在宅医療機器・入れ歯・補聴器や電池・介護用の福祉用具・水と食料・通帳等の番号を控えたメモ


その6 家族みんなで防災会議
災害は、家族がそろっている時に発生するとは限らず、家族がバラバラにいる時に起きる可能性もあります。
日頃から必要な準備をしておくとともに、災害が発生したら落ち着いて、避難・安否確認などの行動をとりましょう。
日頃からできること
〇あらかじめ、災害時にどの親戚や知人等に連絡をするか、また、どの連絡方法を利用するかを家族みんなで決めておきましょう。
〇ふだんから、自宅・学校・職場の近くや、通勤通学途中にある避難所の場所を、家族で確認しておきましょう。
〇保育園、幼稚園、学校、社会福祉施設などにおける、災害時の子どもや家族の引き取りに関する取り決めを、確認しておきましょう。


災害が発生したら
〇被災した場合には、自分の状況を、自分から家族や知人に知らせるとともに、家族の安否を確認することが重要です、ただ、災害発生時に電話が殺到すると、被災地域内における電話がつながりにくくなり、安否確認や、消防、警察への連絡等に支障が発生します、
〇友達同士、親戚同士などで安否情報を素早く正確にリレーすることが大切です。安否確認には、災害用伝言ダイヤル(171)などのサービスを活用しましょう。
〇学校や職場で被災した場合は、先生や防災担当の方の指示に従いましょう。
〇家族の安否と周りの安全が確認できたら、今いる場所で、周囲の人たちと力を合わせて、救出・ 救護活動などに協力しましょう。


その7 ふだんからの地域のつながりが大切です
私たちは、お年寄りや障がいのある方などを支援するために何ができるのでしょうか?
阪神・淡路大震災で、家の下敷きになった人々の多くを助け出したのは、家族や近所の人たち(共助)でした。
大規模災害時の救助や避難などには、ふだんの近所つきあいが力を発揮します。
また、お年寄りや障がいのある方など災害に弱い方々の立場にたった心配りが大切になります。



地域の行事に参加しましょう
町内会や自治会が中心となって開催される行事や集会・お祭りなどで顔を合わせることで、地域の防災に関する取り組みや地域のつながりによる最新の地域情報を知ることができます。
自主防災組織の活動・訓練に参加しましょう
行政区や地域単位で組織している『自主防災組織』での訓練や研修に参加しましょう。
参加型の防災訓練では、安否確認や救出・救護、炊き出しや避難訓練、避難所生活などを体験することができます。