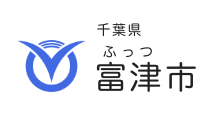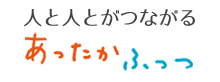あしあと
子ども医療費助成
- 初版公開日:[2023年07月18日]
- 更新日:[2025年8月1日]
- ID:311
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ページ内目次
富津市に住所がある18歳年度末までの子どもの医療に要した費用の一部を助成します。
本制度に関連するSDGsのゴール
本制度は、「SDGs」(別ウインドウで開く)の17の開発目標のうち以下のゴールに関連しています。

子ども医療費助成制度の概要
(1)対象者
富津市内に住所を有する子ども(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)で、保険給付を受けることができる子ども
※対象の子どもが以下のいずれかに該当する場合は助成の対象外となります。
- 婚姻している場合(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
- 就職し、保護者の被扶養者でなくなった場合
- 生活保護を受けるようになった場合
(2)対象となる医療
子どもの入院・通院・調剤の保険診療分
(3)対象の範囲
- 保険給付で医療に要した一部負担金から自己負担額(下表)を除いた額。
(ただし、1人の子どもが、1つの医療機関で、月毎に入院11日目、通院6回目以降は自己負担金無料)
| 世帯区分 | 子ども医療費自己負担金 | |
|---|---|---|
| 入院1日または通院1回当たり | 調剤 | |
| 市町村民税所得割課税世帯 | 200円 月額上限が適用される場合は、 11日目以降の入院及び6回目以降の通院は無料 | 0円 |
| 上記以外の世帯 | 0円 | |
※世帯区分の認定は、毎年7月1日時点の市町村民税の課税状況
申請について
(1)受給券の発行に必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 子ども医療費助成申請書(下記添付ファイル参照)
- 子どもの加入している健康保険がわかるもの(資格確認書など)
- 申請者(保護者)および配偶者のマイナンバーがわかるもの
その他必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。
子ども医療助成申請書 【受給券の申請(出生・転入など)】
注意事項
出生日、または転入日の翌日から一月以内に申請をした場合は、それぞれ、出生日または転入日まで遡ることができます。
一ヶ月を過ぎて申請をした場合は、申請日からの発行となります。
不足書類等の提出用フォーム
不足書類等の提出用フォームとなります。
このフォームで新規申請の手続きはできませんのでご注意ください。
(2)償還払い
領収書の提出による償還払い(口座払い)となります。
(ア)対象者
- 受診時に受給券を忘れた場合
- 受給券対象の子どもが県外にて受診をした場合
- 申請から受給券交付までに医療機関を受診した場合
(イ)申請方法
- 子ども医療費助成金給付申請書(下記添付ファイル参照)
- 1か月分全ての領収書の原本(受診者名・診療点数・領収印のあるもの)
※領収書の返却を希望される方は、ご自分で領収書のコピーをご用意の上で、領収書の原本とコピーを窓口でご提示ください。原本に医療費申請の押印をしてから、原本をお返しいたします。 - 保護者名義の預貯金口座
- 保護者が当該年の1月1日時に富津市に住所を有しないものは、市区町村民税額がわかる書類
- 支払った医療費に対し、高額療養費など他制度より給付を受けた場合は、それが証明できるもの
子ども医療費助成金給付申請書 【助成金の申請】
 給付申請書 (PDF形式、10.65KB)
給付申請書 (PDF形式、10.65KB)ダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類を添付し申請してください。
給付申請書_記入例
注意事項
- 医療機関等が発行する証明(領収書)の申請期限は、医療費等を支払った日の翌日から2年間となります。
受給券を紛失・破損してしまったときは・・・
申請書に必要事項をご記入していただき、窓口にて再交付を受けることができます。
子ども医療費助成受給券再交付申請書
再交付申請書_記入例
このほかにも、こんな時は届出が必要です!
- 子どもの加入している健康保険が変わったとき
- 転居、転出したとき(住所が変わったとき)
- 子どもの氏が変わったとき
- 保護者が変わったとき(生計の中心者)
富津市子ども医療費助成申請変更届出書
医療機関の適切な受診にご協力をお願いします
適切な受診とは
適切な受診とは、「できるだけ医療機関にかからない」ようにするものではありません。
医療機関の受診の仕方を見直すことなどにより、医療機関の受け入れ態勢を整え、「必要なときに、必要な人が、安心して医療を受けられる」ようにするものです。
不要不急の受診などにより、医療やお薬の提供体制がひっ迫してしまうと、必要な人に医療が届かない、そんな状況に陥りかねません。
子ども医療費助成制度は、子育て世帯の医療費の負担軽減として、ご活用いただいています。この制度を安定して継続ができるように、また、必要なときに安心して医療が受けられるように医療機関の適切な受診にご協力をお願いします。
適切な受診のためにできること
こども急病電話相談(小児救急電話相談)を利用しましょう
子ども急病電話相談
電話 プッシュ回線・携帯電話からは 局番なし #8000
ダイヤル回線(黒電話など)、IP電話、光電話からは 043-242-9939
相談日時 毎日・夜間 午後7時から翌日午前8時まで
夜間に急に子どもの具合が悪くなったとき、症状が軽度で医療機関にすぐに受診させたほうが良いか迷われたときにご相談ください。
相談には、看護師や小児科医が電話で応じ、アドバイスが受けられます。
【注意】出血が止まらない、呼吸困難になっている、意識がない(朦朧としている)など、緊急性が高いときは、迷わず119番で救急車を呼んでください。
夜間や、休日に開いている救急医療機関は、緊急性の高い方を受け入れるためのものです。また、医療費も高く設定されていますので、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
参考サイト ONLINE こどもの救急(日本小児科学会)
お子さんの症状をホームページ上にチェック入力することで、夜間や休日などの診療時間外に病院を受診するべきかどうかの判断の目安がわかります(対象年齢は生後1か月から6歳まで)。
外部サイト こどもの救急(別ウインドウで開く)
かかりつけ医を持ちましょう
お子さんのことをよく知る「かかりつけ医」を持ちましょう。
1つの病気で複数の医療機関を受診するのではなく、気になることがあったら、まずは「かかりつけ医」に相談し、お子さんにあった指導や助言を受けられるようにしましょう。
同じ病気で複数の医療機関を受診(重複受診)するのは控えましょう
重複受診は、医療費が余分にかかるだけではなく、重複した検査や投薬によって、お子さんの健康に悪影響となる場合があります。信頼できる「かかりつけ医」を見つけ、まずは「かかりつけ医」に相談するようにしましょう。
重複受診は、治療法を主治医と一緒に判断するために、主治医以外の医師や専門家に意見を求める「セカンドオピニオン」とは異なるものです。
ジェネリック医薬品を有効に活用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先に発売されている医薬品(新薬)の特許期間終了後に厚生労働省の認可のもとで製造、販売されている薬で、成分・効能が同じでも、開発コストが少ないため、価格が安くおさえられた薬です。医師や薬剤師と相談しながら活用についてご検討ください。
ジェネリック医薬品がない場合や切り替えができない場合がありますので、詳細は、医師や薬剤師にご相談ください。