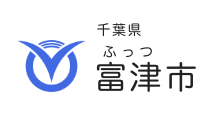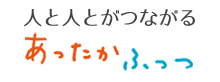あしあと
医療機関にかかるとき(国民健康保険)
- 初版公開日:[2011年01月06日]
- 更新日:[2025年8月5日]
- ID:159
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ページ内目次
医療機関にかかるとき(療養の給付)
医療機関などで、マイナ保険証で受付または資格確認書を提示すれば、診察、治療、薬や注射などの処置、入院、看護、在宅療養、訪問看護などにかかる医療費の一部を負担することで医療を受けることができます。
(マイナ保険証を読み取るカードリーダーに不具合があった際は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示してください。)
| 年齢区分 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 |
| 義務教育就学後から70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割 |
入院したとき
入院したときは、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、同月内の一医療機関への一部負担金の支払いが自己負担限度額までとなり、窓口での支払いの負担を抑えることができます。
入院が決まったときは、限度額適用認定証の交付を申請してください。
※マイナ保険証(健康保険証利用登録が完了したマイナンバーカード)をお持ちの方は、限度額適用認定証の交付申請は不要です。マイナ保険証を医療機関窓口に提示し、高額療養費制度を利用する旨に同意してください。
限度額適用区分、自己負担限度額について詳細は、高額療養費のページをご覧ください。
限度額適用認定証を交付できる方
- 70歳未満の被保険者…保険税に未納のない世帯に属している方
- 70歳以上の被保険者…現役並み所得者2、現役並み所得者1、低所得者2、低所得者1に該当する方
ただし、同一世帯の世帯主及び国保被保険者に所得の申告がない場合は70歳未満ならば「区分ア」、70歳以上ならば限度額適用認定証が交付されない区分と判定します。
手続きに必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 被保険者及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 委任状(別世帯の方が申請する場合必要です)
国民健康保険限度額適用標準負担額減額認定申請書
記入要領

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療などにかかる費用などとは別に、下の表の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
住民税非課税世帯、低所得者2または低所得者1の区分に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより入院したときの食事代の標準負担額が下表のとおり減額されます。マイナ保険証をお持ちの場合は、マイナ保険証を医療機関に提示し、高額療養費制度を利用する旨に同意することで食事代の標準負担額が減額されます。
住民税課税世帯(下記以外の方) | 510円※1 | |
|---|---|---|
住民税非課税世帯・低所得者2 | 90日までの入院 | 240円 |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) | 190円 | |
低所得者1 | 110円 | |
※1 一部300円の場合があります。
標準負担額減額認定証について
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、住民税非課税世帯、低所得者2または低所得者1の区分に該当する方が「限度額適用認定証」の交付申請をすることにより交付されます。また、住民税非課税世帯の70歳以上の被保険者で国民健康保険税の未納がある方には交付申請により「標準負担額減額認定証」が交付されます。
手続きに必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 被保険者及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 委任状(別世帯の方が申請する場合に必要です)
90日を超える入院をしている方の食事代について
住民税非課税世帯または低所得者2の区分に該当する方の過去12か月の入院日数(住民税非課税世帯または低所得者2の区分に該当していた期間の入院日数に限ります。)が90日を超えた場合に入院日数の届出(長期入院該当の標準負担額減額認定証の交付申請)をすることにより、適用日(届出をした日の属する月の翌月の1日)から食事代の標準負担額が240円から190円に更に減額されます。マイナ保険証をお持ちの方でもこの届出は必要です。入院日数91日目から適用日前日までの分として支払った食事代の標準負担額があるときは、申請によりその差額が支給されます。
手続きに必要なもの
長期入院該当の標準負担額減額認定証の交付申請に必要なもの
- 過去12か月の入院日数のわかるもの(医療機関の領収書など)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証(交付を受けている場合のみ)
- 被保険者及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 委任状(別世帯の方が申請する場合に必要です。)
食事代の差額支給申請に必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 医療機関等の領収書
- 被保険者のマイナンバーが確認できる書類
- 世帯主の方の振込口座番号等がわかるもの(預貯金通帳、キャッシュカード等)。世帯主以外の方の口座に振込を希望する場合はその方の口座番号等がわかるものと世帯主からの委任状が必要となります。
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費、居住費を負担します。標準負担額は、下記のとおりとなります。
| 医療の必要性の低い方 | 医療の必要性の高い方 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定難病患者 | ||||||
| 所得区分 | 食費(1食につき) | 居住費(1日つき) | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) |
| 住民税課税世帯(下記以外の人) | 510円(※1) | 370円 | 510円(※1) | 370円 | 300円 | 0円 |
| 住民税非課税世帯・低所得者2 | 240円 | 240円(※2) | 240円(※2) | |||
| 低所得者1 | 140円 | 110円 | 110円 | |||
| 境界層該当者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 | |
※1 医療機関によって470円の場合があります。
※2 過去12か月の入院日数(住民税非課税世帯または低所得者2の区分に該当していた期間の入院日数に限ります。)が90日を超え、入院日数の届出をすることにより適用日(届出をした日の属する月の翌月の1日)から190円に更に減額されます。入院日数91日目から適用日前日までの分として支払った食費の標準負担額があるときは、申請によりその差額が支給されます。
マイナ保険証で対応できないこと
マイナ保険証では対応できないことがあります。マイナ保険証をお持ちの方でも次の場合には交付申請または届出をする必要があります。
- 住民税非課税世帯の70歳以上の被保険者で国民健康保険税の未納がある方が入院したときの食事代の標準負担額の減額を受ける場合(※1)
⇒上記「標準負担額減額認定証について」により標準負担額減額認定証の交付申請をして、交付される標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示してください。 - 長期入院(住民税非課税世帯または低所得者2の区分に該当する被保険者の過去12か月の入院日数(※2)が90日を超える入院)に該当したときの食事代の標準負担額の更なる減額を受ける場合(※3)
⇒上記「90日を超える入院をしている方の食事代について」により入院日数の届出(長期入院該当の標準負担額減額認定証の交付申請)をして交付される長期入院該当の旨の記載のある限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示してください。
※1 有効期限到来により標準負担額減額認定証を更新する場合を含みます。
※2 住民税非課税世帯または低所得者2の区分に該当していた期間の入院日数に限ります。
※3 有効期限到来により長期入院該当の旨の限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証を更新する場合を含みます。