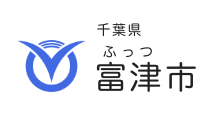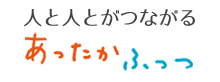あしあと
峰上保育所の保育風景
- 初版公開日:[2013年03月28日]
- 更新日:[2025年12月5日]
- ID:2358
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ページ内目次
峰上保育所収穫祭2025
令和7年11月
保育所で育てたお米やサツマイモを使って収穫祭を行いました!お米は5月に年長児が田植えを行い、草を取ったり、水をあげたりしながら一生懸命お世話をしてくれていました。その甲斐もあり、実入りのいい、ふっくらしたお米をたくさん収穫することができ、とても喜ぶ子ども達。“大きなおにぎりにして食べるんだ♪”と、収穫祭を心待ちにしていました。
しかし、お米を食べるためには収穫して終わりではありません。脱穀やもみ摺りなどさまざまな過程を経て、ようやくおいしく食べることができます。もちろん、全て手作業で行うので、園全体で力を合わせて頑張りました。
脱穀は牛乳パックを使って行いました。牛乳パックの飲み口に稲を挟んで引っぱると“プツプツプツ…”という音と共にお米が取れていきます。地道な作業ですが「もう、こんなに集まったよ♡」と嬉しそうに中をのぞきながら、お米を集める姿が見られました。
もみ摺りは、すり鉢と野球ボールを使って行いました。もみ殻付きのお米をボールでゴリゴリ摺って、フーッと息を吹きかけると、もみだけが飛ばされ玄米が姿を見せます。だんだんと見慣れたお米に近づいていく様子に、「おぉー!」感動の声をあげていました。
大きい組が主となって籾摺りを行っていると、1、2歳児のお友達もお手伝いをしてくれました。もみ摺りの様子は普段から目にしていたこともあってか、戸惑うことなく作業を進める姿に保育士もびっくり!
また、大きい組が「こうやるんだよ」と優しく教える姿も見られ、大きい子への憧れの気持ちや、小さい子への思いやりの気持ちが、普段の生活の中で自然に育まれていることを感じました。
そして迎えた収穫祭当日。お米を研いで羽釜にセットしたり、畑で採れたサツマイモを使って豚汁作りをしたりと、朝から大忙しの子ども達。しかし、“やっとお米が食べられる”と楽しみにしていたこともあり、とっても張り切って取り組んでくれました!
この日は、年長児が薪割りや火起こしにも初挑戦!「年長さんだけの特別だよー」と声を掛けると、「やったー!」と飛び跳ねて喜ぶ姿がとても可愛らしかったです。初めてのことに最初はちょっぴり不安そうな様子を見せていましたが、上手に薪を割ったり、火を起こしたりすることができると「できた!」と、とびきりの笑顔を見せていました。“年長児だけ”という特別感を味わうことがで自信にもつながり、更に頼もしさが増したように感じます。
収穫祭には、在園児の保護者でもある【田んぼの先生】を招待し、一緒に給食を食べました。みんなで作った豚汁や炊きたてご飯を「おいしい!」と言ってモリモリ食べてくれ、子ども達も大喜び!楽しい時間を過ごすことができました。そして最後に、田んぼの先生がサプライズ、お米で作るお菓子【ポップライス】を作ってくれました。ほんのり甘くてサクサク食感のポップライスを食べ、子ども達の笑顔も弾けていました。もみ殻付きのお米でしか作ることができないようで、お米作りをした人だけが味わうことのできる貴重な経験ができました。
お米や野菜作りの大変さを感じながらも、成長や収穫することの楽しさ、自分達で作って食べることの喜びを味わうことができました!
運動会頑張ったよ!
令和7年10月
さわやかな秋晴れのもと、峰上保育所運動会を行いました。今年は『大好きなことを大好きなお家の人に見てもらったり、一緒にやったりしたい』と子ども達が意見を出してくれ、大好きが詰まった運動会に決まりました。リレーや玉入れなどの定番競技に加え、先月のホームページでもお知らせしたコーン倒しや盆踊りなどさまざまな競技が盛りだくさん!どの競技を行っている時も子ども達、お家の人達の笑顔が溢れていて、みんなの気持ちが一つになったステキな運動会となりました。
今回のホームページでは、そんな楽しかった運動会の名場面をご紹介したいと思います。
玉入れは子ども同士で勝負をした後、おじいちゃん・おばあちゃんと勝負をしました。子ども達の気合に負けないくらい気合十分な戦いっぷりを見せてくれたおじいちゃん・おばあちゃん。
見る見るうちにカゴは玉でいっぱいになり、結果はなんとおじいちゃん・おばあちゃんチームの勝利!子ども達は「えー!」「もう一回勝負だ!」と悔しさを見せていましたが、お孫さんと一緒にできるという喜びが大きかったからこそ、夢中になって楽しんでくれたんだなと感じました。
次に行った玉のお片付け競争では、子ども達の様子を気にして片付けのスピードをさりげなく調整してくれたので、勝利の栄冠は子ども達の手に!今度は勝つことができたので、子ども達は「やったー!」とジャンプをして喜んでいました。最後は、可愛いお孫さんにちゃんと花を持たせてくれる優しいおじいちゃん・おばあちゃんの姿に気持ちが温かくなりました。
『新富津音頭』を踊る時は、観覧に来ていたほとんどの方が参加してくださったので、園庭にとても大きな円ができあがり、まるでお祭りのような雰囲気の中で盆踊りを楽しむことができました!
初めての方も戸惑わないように、踊りの得意なお家の方に【踊りの先生】になってもらい、職員と一緒に円の中心でお手本として踊っていただきました。老若男女問わずみんなで参加することができたので、更に気持ちが一つになり、絆も深まったように感じます。
新富津音頭を踊っていることをお家の方に伝えてはいましたが、踊っている子ども達の姿を見るのは初めてだったので「こんなに踊れるの!?」「上手だね!」と、とても驚いていました。実際に一緒に踊ったことで、子ども達が普段行っていることの楽しさはもちろんですが、大変さや難しさなども肌で感じていただけたように思います。
また、富津市ならではの競技を取り入れたことで、自分達の住んでいる地域の魅力を改めて感じることができました♪
閉会式では、金メダルと素敵なプレゼントをもらい、キラキラスマイルを見せる子ども達。自分達の頑張っている姿を大好きなお家の人に見てもらったり、応援してもらったり、認めてもらえたりしたことが大きな自信となり、一段と頼もしさが増しました。
また、運動会が終わった後もコツコツと雲梯の練習を続け、見事できるようになったお友達も居ました。運動会があるから練習するのではなく、“できるようになりたい”という気持ちを持って取り組んでいるからこそ、諦めずに挑戦していて、子どもの主体性が育まれてることを感じました。
これからも、子ども達の“やってみたい”“楽しい”という思いを大切にしながら、さまざまな活動を一緒に作り上げていきたいと思います。
体を動かすって楽しい!
令和7年9月
今年の9月は残暑が厳しかったですね。熱中症リスクも高く、子ども達も思うように外で遊ぶことができない日が続きました。しかし、保育士と子ども達でアイディアを出し合って身近な物を使ったゲームを考え、室内でもたくさん体を動かして楽しく過ごすことができました!
三角コーンを倒すチームと起こすチームに分かれて遊ぶ『三角コーン倒し』では、毎回白熱した戦いが繰り広げられました。時々、相手チームのお手伝いをしてしまう『スパイ』が現れることもあり、そんなところも可愛らしく見どころの一つです。「違うよ!〇〇ちゃんは倒す方だよ」「あれ?そうだっけ?」などと子ども同士で教え合う姿も見られ、考えたり協力したりしながら楽しく遊んでいます。
『ゴルフ対決』では、ホールインワンを狙い真剣な表情でクラブを握る子ども達。フォームも様になっていて、まるでプロゴルファーのようです。フープの中にボールを入れるのは意外に難しく、調整力が必要ですが「もうちょっと強く打ってみようかな?」「今度は跳びすぎちゃった…」と試行錯誤しながら、とても集中して遊ぶ姿が見られました。
3歳以上児が『綱取り』で楽しそうに遊ぶ姿を見て「やりたい!」と1,2歳児。「よーい、どん!」という合図を聞き、勢いよく走っていく姿がとっても可愛いです。普段から大きい組のやっていることに興味津々な1.2歳児達は、“同じことをやってみたい”という気持ちが強く、さまざまなことに意欲的に取り組んでいます。一緒に過ごしているからこそ自然と憧れの気持ちが芽生え、成長につながっていることを感じます。
0歳児のお友達も、ハイハイでトンネルをくぐったり、マットの山をよじ登ったりして、たくさん体を動かして遊んでます。平らな場所で遊ぶだけでなく、坂道や段差などを意識的に遊びの中に取り入れることで、運動機能の発達につながり体幹も鍛えられるので、小さな頃からたくさん体を使って遊ぶことを大切にしています。
また、体操代わりにみんなで『新富津音頭』も踊っていました!子ども達にはあまり馴染みのなかった盆踊りですが、今では「今日、富津音頭やろうよ!」と保育士にリクエストするほどお気に入りになっています。
このように、普段から身近な物を活用して運動遊びを楽しんでいる子ども達。「お家の人と一緒にやったら、もっと楽しいかもしれない!」という話になり、今年の運動会で取り入れることにしました。もちろん、リレーや玉入れなどの定番競技も行いますが、普段の遊びを運動会風にアレンジし、子どもから大人まで家族みんなで楽しめる競技が盛りだくさんの運動会です。日頃の活動が自然と行事に繋がっていき、子ども達も無理なく自然体で取り組むことができています。
プールに行ったよ!
令和7年8月
ふっつんバスに乗って、金谷海浜公園プールに遊びに行きました。今年2回目のプールへのお出かけは竹岡保育所のお友達も一緒でした。竹岡保育所のお友達とは、磯遊びを通して交流をしてきたので、すっかり仲良し!お互いの名前を覚えていたり、「〇〇君と結婚するんだぁー」と言ったり、一緒にプールへ行くことをとても楽しみにしていました。
バスを降りた後、プールまでの道のりは竹岡保育所のお友達と手を繋いで歩いていきました。久々の再開を喜び合う子ども達。まるで入所してきた時からの友人のように、おしゃべりを楽しみながら歩いていました。
4月からは環小学校も天羽小学校と合併します。このように交流する機会を持つことで、子ども達も安心して小学校に通うことができるようになると思います。
いざ、楽しみにしていたプール遊びへ!ビート版を使って泳ぐ姿が様になっているA君。とびきりの笑顔を見せながら、とても気持ち良さそうに泳いでいました。前回のプール遊びの時は、プールの深さに不安そうな表情をする子も居ましたが、2回目ということで様子も分かりのびのびと楽しむ姿が見られました。
まだ、水に潜ることに抵抗があるBちゃん。しかし、“潜れるようになりたい”という思いは強く、保育士と一緒に練習に励んでいました。「こうやってやるんだよ」と実際に潜る姿を見せ、体を張って潜り方を伝える保育士。“先生も一緒”という安心感が、子ども達の“やってみよう”という気持ちを更に大きくしていることを感じます。
保育士と手を繋ぎ、水に顔を付けることに成功すると「できたぁ!」と、嬉しそうなBちゃん。またひとつ大きな自信となりました。
竹岡保育所のY保育士ともこんなに仲良くなりました♡背中におんぶしながらプールの中を歩いてもらい、大喜び!峰上保育所には男性の保育士さんがいないので、パワフルなY保育士と一緒に遊んでもらうことができ、とっても嬉しそうでしたよ。自園の保育士だけでなく、他園の保育士とも自然に関わりおもいきり遊ぶ姿を見て、小さいうちからいろいろな人と関わることが、コミュニケーション能力を高めていくきっかけになるのかなと思いました。
広いプールでたくさん遊んだ後は、竹岡保育所にお邪魔して一緒に給食を食べました。たくさんの楽しい気持ちを共有し、更に絆を深めることのできた1日でした!
夏のお楽しみ会2025
令和7年7月
7月31日(木曜日)に、夏のお楽しみ会を行いました!今年のメインイベントは、子ども達によるファッションショー『MGC(峰上ガールズコレクション)』です。年長児がカラーポリ袋を使ってお洋服を作ったり、着て歩いていたりしている姿をきっかけに、年少・年中児も巻き込んだファッションショーごっこへと遊びが発展。「みんなにも見せたい!」と、子ども達がとても夢中になっており、お楽しみ会でファッションショーを開催することになりました。
自分で作った衣装を身にまとい、ステージから登場してランウェイを歩く姿は、とってもキュート♡ポーズもばっちり決めていて、本物のモデルさんのようでした。人前に立つことが苦手なお友達もファッションショーでは1人で立派にランウェイを歩いていて、普段の遊びの中での何気ない経験が子ども達にとっては大きな自信になることを感じました。
ファッションショー終了後は、展示即売会を行いました。洋服だけでなくシーグラスや貝がらで作ったアクセサリーも販売していて、あっという間に完売するという大盛況ぶり!もちろん支払い方法は、先月のホームページで紹介したお店屋さんごっこ同様『バーコード決済』となっていて、レジを待つ時間も短縮されスムーズな購入につながりました♪
休憩を挟んで、今度はお店屋さん巡りを楽しみました。お菓子のつかみ取り・アイス・ヨーヨーと3つのお店屋さんがあり、すべて巡るとオモチャがもらえるというサービス付き。これはハッピーセットを頼むともらえるおまけのオモチャをイメージしたシステムとなっているようで、年長児がアイディアを出してくれました。こんなところにも普段の経験が生かされていて、工夫して遊びに取り入れています。
今年のお楽しみ会は、まだまだ終わりません!午後は先生たちからのサプライズプレゼントということで、じゃがいもピザを作って子ども達にご馳走し、プラネタリウムの上映を行いました。畑で採れたじゃがいも・トマト・ナス・ピーマンを使ったピザは大好評!また、プラネタリウムでは天井に星が映し出された瞬間「うわぁー♡」と歓声を上げ、とても嬉しそうに星を眺める子ども達でした。
そして最後に、8月から産休に入るT保育士が元気な赤ちゃんを産めるようにと、みんなでお星さまにお祈りをして、手作りのお守りをプレゼントしました。
楽しいことが盛りだくさんの1日となり、大満足の子ども達でした。
お楽しみ会の翌日「自分達もプラネタリウム作りたい!」と言って、画用紙に型抜きで穴をあけてカラーセロファンを貼り、自分だけのプラネタリウムを作成して、テーブルに投影させて楽しんでいました。「お家でも作ろう♪」と、すっかりプラネタリウムのとりこになっていました☆
お店屋さんごっこで遊んだよ!
令和7年6月
今年は、畑の野菜が大豊作!収穫した野菜は子ども達がクッキングしたり、給食に入れてもらったりして、毎日おいしくいただいています。
この日は、人参・ナス・キュウリ・トマトがこんなにたくさん収穫できました。「どうやって食べようかなー?」と悩む子ども達。しかし、あまりにもたくさんありすぎて食べきることが難しそうだったので、お家に持って帰ることにしました。
みんなで仲良く分けるにはどうしたら良いのか…?と考えた結果、八百屋さんを開き、お買い物ごっこをしながら持ち帰る野菜を決めることになりました。
店先に商品を並べ、レジをセットして準備は万端。『峰上直売所』のオープンです!商品をレジへ持って行くと、店員さんが「ピッ!」と言いながらスキャンし、袋詰めまで行ってくれるのでとっても親切です♪
お買い物ごっこは、子ども達が大好きな遊びなので、普段からみんなでよく遊んでいます。店員さんのお客さんさばきもとってもスムーズで、慣れた手つきで接客していました。
「どれにしようかなー?」と真剣な表情で、野菜を手にする子ども達。レジに持って行ける野菜の数は1つと決まっていたので、“1番いい野菜を持って行かなくては!”と、とても時間をかけて選んでいました。
子ども達から人気があったものは、なんといっても大きな野菜!「これにしよう!」と手にした後も「やっぱり、こっちの方が大きいか…」と、より大きな野菜を選んでいく、ちょっぴり欲張りな子ども達に笑ってしまいました。こうして野菜を選びながら、数や大小の概念も自然と身についていくように思います。
購入方法は、なんと『バーコード決済』です。手作りスマートフォン(使用者側からQRコードが見えるよう真ん中に穴が開いています)で、レジの横に置いてあるQRコードを読み取ると店員さんが「ペイペイ♪」と言ってくれるのです。とても画期的ですね!最新の機器を子ども達は熟知していて、保育士の方が驚かされることが多々あります。
また、お家の方にその様子を伝えると「うちはペイペイ使ってないのになぁー」と不思議そうすることも…。きっとお買い物に行った時などに目にしていたのでしょうね。子ども達はいろいろなことをよくみているなぁと、感心します。
保育所では日々の何気ない経験が、遊びに活かされています。子ども達が実際に肌で感じて得た経験だからこそ、工夫しながら遊びに取り入れ、みんなで楽しむことができるのですね。
木登りに挑戦!
令和7年5月
峰上保育所の園庭には、たくさんの桜の木が植えられています。その中に絶好の木登りスポットがあり、子ども達のお気に入りの場所になっています。木の上から眺める景色は最高なようで、「やっほー!」と下にいるお友達に手を振り上機嫌!順番待ちをしているお友達から「早く降りて来てよー」と言われ、「やーだよ!」と時には言い合いをしながらも、夢中になって遊んでいます。
お友達同士で「ここに足掛けてみれば?」「もうちょっとだよ、頑張れ!」と声を掛け合ったり、登れた時は「やったね!」と大きな拍手をして自分のことのように喜んだり、子ども達の仲間意識も強まってきていることを感じます。
木登りをする際は、子ども達が自分の力で登ることを大切にしています。もちろん、保育士が側について見守り、必要に応じて体を支えてあげることはありますが“自分でできた!”と子ども達自身が実感できるような関わりを心掛けています。
また、安全面から見ても自分で登れる高さというのはとても重要です。“ここまではできそう”“これ以上はやめておこう”と自分で判断できる力をつけることが怪我防止にも繋がっていきます。“簡単そうに見えたけど、やってみたら難しかった…、怖かった…”など、やらないと分からないことがたくさん。そのような経験ができる機会を大切にしていきたいです。
最初は木の根元にしがみつくのが精一杯だった年少児のA君も、今ではこんなに上まで登れるようになりました。「おーい!ここに居るよー!」とみんなに声を掛ける姿は、とても嬉しそう!そして、“自分でできた”という達成感・充実感を味わうことができ、誇らしげな表情です。
何の変哲もない『木登り』ですが、どこに手や足を掛けようかと考えたり、自分の力で体を支えたりして登る中で、判断力や体の使い方、バランス感覚などさまざまな力が育まれているのを感じます。
また、“楽しそう!やってみたい!”というドキドキ・ワクワクがあるからこそ、できるようになるまで諦めない粘り強さにも繋がっています。
オモチャなどなくても、そこに木があれば子ども達にとっては楽しい遊び場に大変身!自然の中でたくさん遊びながら、心も体もたくましく成長している子ども達です。
キャベツが採れたよ!
令和7年4月
昨年度から育てていたキャベツが食べ頃になったので、くま組(5歳児)がお料理をしてくれました。「どうやって食べようか?」と、みんなで相談をしたところ…ゆでたキャベツを『塩・マヨネーズ・ソース・醤油』の4種類の調味料ごとに分けて、食べ比べをすることになりました。「どの味が1番おいしいかなー?」と、ワクワクの子ども達です。
身支度を整え、さっそくクッキングスタート!
もちろん、エプロンも自分で身に着けます。出来ないところは「手伝って」とお友達同士で協力し、一生懸命お支度していました。三角巾がちょっぴりずれているところは、ご愛嬌。“できるところは、自分で”を大切にしています。
まずは、キャベツをきれいに水洗い。無農薬栽培なので虫がついていることもあり、子ども達は『キャー!』と大騒ぎをしながらも、一枚一枚丁寧に洗ってくれました。虫も食べに来るほど、おいしいという証拠ですね。
ゆであがったキャベツを4種類の調味料ごとに和えて、さっそく食べ比べてみました。どの味も「おいしい!」と子ども達は大喜び。特にどの味が美味しいのか「いっせーのーで!」で指差しをしてみると、『マヨネーズ』と『塩』の2つに意見が分かれました。
いい匂いに誘われて、お外で遊んでいたA君が「何してんのー?」と、お部屋の中を覗き込んできました。「キャベツ食べる?」と声を掛けられ、“待ってました!!”と言わんばかりの勢いで手を洗いに行く姿が見られました。そして、他のお友達にも「みんなー!キャベツあるよー!」と教えてあげており、楽しいことをみんなに共有してくれる優しいA君でした。
採れたてキャベツはとってもおいしかったようで、「もっとちょうだい!」と言って手を伸ばしてくる子ども達。その光景はまるで、ひな鳥がエサをもらっているかのようで可愛らしかったです。
畑には、近所の方に頂いたロメインレタスや人参が植えられています。これから夏野菜の栽培も行っていくので、旬の野菜をおいしく味わっていきたいと思います。
☆おまけ☆
キャベツに付いていた青虫を飼育ケースに入れて育てていると…なんと、さなぎに変身!!「どんな、ちょうちょになるかな?」と、楽しみにしている子ども達です。
くまぐみさん、ありがとう!
令和7年3月
卒園・進級が間近になった3月。環境が変わることへのドキドキやワクワクを感じながら、日々過ごしている子ども達。残り少ない日々の中で、大好きなお友達と過ごす時間を大切にしながら日々を過ごしています。
みんなで一緒に行ける最後の遠足『お別れ遠足』では、子ども達のリクエストで鴨川シーワールドに行きました。大迫力のシャチのショーや可愛いペンギン、さまざまな海の生き物を間近で見ることができ、大喜び!「次、あっちに行こう!」「あれ見たい!」と、パワフルにシーワールド内を巡っていく子ども達に、保育士がついていくのがやっとな程…。しかし、子ども達が心の底から楽しんでいる様子が伝わってきて、保育士も嬉しくなりました。
お別れ遠足の他にも、ピザ作り体験に行き自分達で生地を伸ばしてトッピングしたピザを食べたり、新しくなった富津警察署の見学に行ってお巡りさんのお仕事を見せてもらったりしました。
また、在園児がこっそり企画したお別れ会も行いました!大好きなくま組への“ありがとう”がたくさん詰まった企画が盛りだくさんになっていて、一緒にオリエンテーリングをしたり、ダンスを踊ったり、うさぎ組が作ったホットケーキを食べたりとスペシャルな1日となりました。みんなの絆もさらに深まり、とっても素敵な思い出となりました。
4月からはピカピカの1年生になる、くま組さん。卒園式には、自分達で苗を選んで育ててきたパンジーをステージに飾りました。「早くお花咲かないかなー」「何色の花が咲くかな?」と毎日水かけをして大事に育ててきたので、お花が咲いた時の喜びもひとしおでした。
小学校に行っても自分らしさを忘れずに楽しく過ごし、『自分だけの素敵な花』を咲かせてほしいなと思います♪
冷たいけど、楽しさいっぱい!
令和7年2月
立春を迎え、少しずつ寒さがやわらいでくるかと思いきや、寒さが一段と厳しさを増した2月中旬。そんな寒いある日、園庭で氷を見つけました。「氷、あったよー!!」と、大興奮でお友だちに伝える姿は、まるで宝物を見つけたかのような嬉しそうな表情です。
小さくて薄い氷は、みんなで触っているうちにあっという間に溶けてしまったので「もっと、たくさんの氷が欲しい!」と、氷作りをすることにしました。
早速、バケツに水を入れて、テラス前にあるイチョウの木の根元に置いてみました。
次の日、「氷できたかなー?」と、子ども達が期待に胸を膨らませながら様子を見に行くと、氷にはなっておらず「できてない…」とがっかり…。
「あんまり、寒くなかったのかな?」「違うところに置いた方がいいのかな?」と試行錯誤を繰り返した結果、今度は、寒そうな畑や園舎の裏に水を張ったバケツを置いてみることにしました。
またまた次の日、「今日は氷できたかなー?」と、ドキドキしながら様子を見に行ってみると…、なんとそこには立派な氷が!!「やったー!氷になった!」と大興奮の子ども達。「見て、見て!おっきい氷できたよー」と、とっても嬉しそうにお友達や先生と見せ合って楽しんでいました。
お水に花びらや葉っぱを浮かべ、凍らせることができるか?ということも試してみました。結果は、見事大成功!透明な氷の中に、ピンクや黄色の花びらや葉っぱが映えて、とってもきれいな氷ができました。世界にたった一つの、自分だけのオリジナル氷に大満足の子ども達でした。
お顔と同じくらいの大きさの氷を、お面のようにして「はい、チーズ!」。氷越しに見る景色に「キラキラしてるー」と大はしゃぎ。普段とはまた違った世界を見ることができたようです。
この時期にしかできない氷遊び。考えたり、試したり、驚きや喜びなどをみんなで分かち合ったりしながら、寒い冬でも元気に楽しく過ごすことができました!
赤ちゃんかわいいな
令和7年1月
峰上保育所に、4ヶ月の赤ちゃんが仲間入りしました。まだ、他のお友だちとは生活リズムが違うため、職員室で過ごしているのですが、赤ちゃんのことが気になって仕方ない子どもたち。「赤ちゃんは?」「寝てるの?」と様子を見に来ては、声をかけたり、あやしたりして、とてもかわいがってくれています。
時には、泣き声を聞きつけ職員室に来てくれることもあります。「遊んであげるね♪」とオモチャを持ってあやす姿は、まるで小さな保育士さん。絶妙なタイミングでお手伝いしてくれるので、保育士も大助かりです。
ベビーカーで園庭をお散歩していると、ベビーカーの周りにはあっという間に人だかりが!「お手伝いするー」と言って一緒にベビーカーを押してくれたり、「いない、いない、ばぁ!」と遊んでくれたりするので、赤ちゃんも笑顔を見せて嬉しそうにしています。その姿をみて「かわいいー♡」と、さらにメロメロになるお兄さん・お姉さん達です。
1歳になったばかりのお友だちも、赤ちゃんをとってもかわいがってくれています。つい数ヶ月前までは、自分達もミルクを飲んでいたのに、赤ちゃんを見つめる眼差しはすっかりお姉さん!優しく頭をなでてあげたり、話しかけたり、自分達がしてもらった心地良い体験を返してあげているのだなと感じます。
くま組(5歳児)が、とても優しそうな表情で赤ちゃんを見つめている姿に、職員も気持ちがほっこり♡みんなの表情からは、心から可愛がってくれている様子が伝わってきます。
保育所では、クラスに関係なくさまざまな年齢のお友だちが自由に交流し、たくさん関わりを持ちながら過ごしています。一緒に遊んだり生活したりする中で、小さい子への思いやりの気持ちや大きい子への憧れの気持ちが、自然と育まれているのを感じます。
0歳児から5歳児までの幅広い年齢との交流は、保育所だからこそできる貴重な体験だと思います。さまざまな年齢のお友だちとの関わりを通して、社会性や協調性、コミュニケーション力など、社会に出た時に大切になる力の基礎を培うことができればと思います。
習字に挑戦!
令和6年12月
くま組(5歳児)が、習字に挑戦しました!書いたのは、令和7年の干支『へび』という文字。教えてくれたのは、習字が得意なS先生です。
習字のセットを前にした子ども達は、保育士が声をかけても“うん、うん”と首を振るだけで、いつになく緊張した表情に…。「習字やるんだー!」と朝から張り切ってみんなに自慢していたものの、実際に道具を前にしてみると“習字っていったい何なんだ…?”“今から、何をするんだ?”と、ちょっぴり不安になりドキドキしてしまったようです。
最初は「筆に親しもう!」ということで、自由にお絵描き!「何でも好きなものを描いていいよ」と言われ、少しだけ緊張がほぐれた子ども達は、グルグルと線を描いたり、お顔を書いたり、思い思いにお絵描きを楽しみました。中には、雪だるまの絵を描く子も居て、子ども達の自由な発想に驚かされる保育士達。「すごい!上手だね!!」と見ている保育士の方が興奮気味に声をかけていました。この頃にはすっかり緊張もほぐれた子ども達は、笑顔を見せながら生き生きとした表情で筆を走らせていました。
絵を描いていくうちに、だんだんと力の入れ方も分かってきた子ども達。筆の持ち方も様になってきたところで、いよいよ干支の文字『へび』を書いてみました!バランスを取ったり、『び』という字のカーブを書いたりするのに苦戦する子も居ましたが、慎重に筆を運び一生懸命作品を仕上げていました。1枚書くごとに「できたよ!」と目をキラキラさせながら見せてくれ、“上手でしょ!”と言わんばかりの表情が可愛らしかったです。
漢字で自分の名前を書くことにも挑戦!お手本とにらめっこしながら書く姿は、とっても真剣です。出来上がった作品は、まるで書道家が書いたかのような味のある作品に仕上がっており、一文字一文字丁寧に書いた様子が伝わってきて、とっても上手でした。
普段、文字のワークをやる時は「まだあるのかー」と、疲れた様子を見せることもありますが、この日はそんな言葉は一切無く、とっても集中して取り組んでいました。“楽しい”“もっとやってみたい”というドキドキ・ワクワクがあるからこそ夢中になれるのでしょうね!
完成した作品は、画用紙の台紙に貼って玄関に飾りました。台紙があることで、ぐっと素敵さも増したように感じます。他のクラスも、お正月にちなんだ作品を作って飾り、玄関はとても華やかに!送迎に来た保護者に「今日、これやったんだよ!」と、自分の作品を紹介する子どもたちの表情は、とっても得意気でした。
「楽しかったから、またやりたい!」という子も居て、字を書くことの楽しさを味わい、文字への興味関心も高まったように感じます。また、日本の文化にも触れることができ、貴重な体験となりました。
お問い合わせ
電話・ファクス: 0439-68-0080