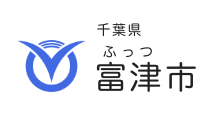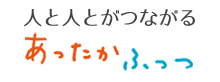あしあと
中央保育所の保育風景
- 初版公開日:[2013年03月28日]
- 更新日:[2024年3月26日]
- ID:2352
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ページ内目次
門松作りを見に行ったよ
令和7年12月
保護者の方に “門松作りをしている所がある”と教えていただき、うさぎ組(3歳児)・くま組(4歳児)・ぞう組(5歳児)のみんなで見に行ってきました!寒くても元気いっぱいの子ども達。はりきって出発し到着すると、たくさんの竹に「すごーい」「いっぱいある!」と目が釘付けでした。
作り方を順番に見せてもらったり、竹の配置や切り方によって願うことが違ったり、いろいろなお話を聞かせていただきました。土台に藁を巻き付け、縛るところを見せてもらった時には子ども達から「おぉー!!」と拍手が起こりました。「この竹はどこから持ってきたの?」「何でこんなにきれいな緑なの?」「できた門松はどこに飾るの?」などなど、子ども達や保育士の疑問にも一つひとつ答えてくださいました。門松を作っている所を間近で見させてもらい、とっても貴重な時間となりました。最初は「門松って何?」と思っていた子もいましたが、この経験を通して、今後門松を見かけた時に「保育所のみんなで見に行ったやつだ!」と、少しでも日本独自の正月飾りを意識してくれたらいいなぁと思います♪
そして、門松作りをしているお家には大きなコンバインがあり、車庫から出して見せてくれました。動く度に「わぁー!」「かっこいい!」という歓声とともに拍手をする子ども達の姿がほほえましかったです。
特別に運転席に一人ずつ乗せてくれました!この表情が何とも言えません♡
地域の方々のご協力でいろいろな経験ができ、幸せな子ども達です♪
親子あそび会
令和7年11月
どんぐりじーこと吉澤さんにお越しいただき、自然物を使った製作をおうちの方と一緒に楽しみました。
お散歩の際に自分で拾ってきたどんぐりに加え、どんぐりじーが木の実や枝、種など持ってきてくださり、その中から自分の好きなものを選びました。顔が描かれているものなどたくさんの種類があり、目をキラキラさせながら「どれにしようかな」と、おうちの方や保育士と会話する姿がほほえましかったです。
選び終わると早速ボンドやグルーガンを使って、土台の木にそれぞれ好きなようにつけていきます。はしごやお家、ベッド、鳥、帽子などの形に作ったものもあり「ここにつなげる!」「ここにつけたい♪」「あぁ取れたー!」など親子の会話を楽しみながら、みんなが集中して取り組んでいました。「もっとつけたい!」と追加で木の実や種を選びにくる子がほとんどで、いつも元気な子ども達がこんなにも集中し、あっという間に時間が過ぎたことに驚く保育士でした。
サンタクロースをいっぱいつけたり、つなげてつなげて大きなお家を作ったり、一人ひとり個性あふれる素敵な作品が完成!!「まだやりたい!」という子もいましたよ。
木の実や種など自然物は種類によって一つひとつ形や色など違い、発見がたくさんありました。そんな所も楽しみながら、改めて自然の力はすごいなぁと感じた活動でした。
茶道体験
令和7年10月
地域の茶道の先生にお越しいただき、茶道体験をしました。初めての体験に子ども達は興味津々。茶室のようにセットされた空間にちょっぴり緊張気味の子もいました。掛け軸はぞう組(5歳児)の手作りです。
赤い絨毯に座ると、なんだか背筋もピンとします。お辞儀の仕方から教わり、茶筅で自分のお茶を点てました。泡立つように混ぜるのは「難しいー!」と苦戦しながら、ぐるぐると慎重に混ぜていました。一緒に添えられていた普段食べないようなかわいい和菓子、食べてみると「おいしい!」「あまーい♡」と大好評でした。
そしてついに自分で点てたお茶を頂きます。茶碗の絵の所を汚さないようにくるっとまわし、ゴクッ・・・「おいしーい」「にがーい」と感想はさまざまでした。飲み終わるとまた茶碗をくるっとまわし、元に戻します。
ぞう組はお茶出しもやってみました!こぼさないようにそろりそろりと歩きます。
タイミングを見てお茶を出したり、茶碗の絵を相手に見えるように置いたり、その他にもたくさんの思いやりが込められていて、奥が深い茶道でした。温かい雰囲気の中、子ども達だけでなく保育士もおもてなしの心を学び、日本の文化に触れた素敵な時間となりました。
おまつりうんどうかい
令和7年9月
夏のあそびを思いきり楽しんだ子ども達は夏の終わりにはたくましく成長し、保育者との水かけ合戦など対戦を楽しむようになりました。その気持ちが、運動会へと向いていき、玉入れ・綱引き・リレー・跳び箱・鉄棒などさまざまな運動遊びへとつながっていきました。
夏のお楽しみ会で作ったお神輿を「おうちの人にも見せたい!」「おまつりのように楽しい運動会にしたい」というぞう組(5歳児)の思いから、今年の運動会のテーマは「おまつりうんどうかい」になりました。どのクラスもおまつりにちなんだ競技を子ども達と保育者で一緒に考え、楽しみながら準備してきました。その中で、ぞう組は鉄棒、跳び箱、ソーラン節も挑戦。「やりたい!やりたい!」と張り切って取り組み、どんどん上達していく子ども達でした。でも時にはうまくできなかったり、思うように踊れなかったり、悔しい気持ちを感じている子もいました。どうしたらできるか、その都度自分なりに考えながら、頑張る姿に成長を感じました。そんなお兄さん、お姉さんの姿を見ていたことり組(2歳児)、ひよこ組(0・1歳児)のお友達。「かっこいい!」「すごーい」と目が釘付けになったり、真似をしたり、憧れの気持ちが大きく膨らんでいます。
そして当日(10月4日)。オープニングはひよこ組が乗った手作りの山車をうさぎ組(3歳児)・くま組(4歳児)が引っ張り、ことり組は提灯を持って登場しました。その後はうさぎ・くま組が竹太鼓のお囃子を響かせる中、ぞう組が手作りのお神輿で「わっしょいわっしょい」と元気なかけ声と共に「そりゃあそりゃあ」とお神輿を高く持ち上げながら登場しました。「すごーい」「かっこいいー」「かわいいー♡」とおうちの人や来賓の方にたくさんの拍手をもらい、嬉しそうな子ども達でした。所長先生神主さんに運動会が楽しくできるようお祈りもしてもらい、競技がスタート!
各クラス楽しみながら競技を進めていると・・・仮装したおうちの人達が現れ、綱引きで勝負しようということになりました(子ども達にはサプライズ!)。そして見事子どもチームの勝利!!年長児の保護者が協力してくださり、会場中が笑顔でいっぱいになりました♪
その他、おじいちゃん・おばあちゃん・来賓の方と玉入れで勝負したり、借り物(人)競争があったり、みんなが一体となり、温かい雰囲気の運動会となりました。
前日の天気予報では雨が心配だったので、てるてる坊主を作り「運動会やれますように」とお祈りした子ども達。当日は最後の方で雨が降ってきてしまいましたが、子ども達は気にもせず、最後までよく頑張りました!
来賓の方もたくさん来てくださり、とっても楽しい運動会になりました。たくさんのご協力ありがとうございました!
夏のお楽しみ会☆
令和7年8月
夏のお楽しみ会に向けて、どんなことをやろうかと話し合いを進めてきたぞう組(5歳児)。昨年のお楽しみ会で出店が楽しかった経験から今年も「おまつりをやりたいね」ということになりました。おまつりといえば「お神輿」と「出店」のイメージの子どもたち。“自分たちでお神輿を作りたい”と、地域の方のご協力でお神輿を実際に見学させていただきました。キラキラしているお神輿に目が釘付け!「あぁいうのにしたいなぁ」とイメージをふくらませていました。
お店屋さん(出店)の準備も毎日コツコツと進め、無事にお神輿やお店屋さんに必要なものが完成しました。真剣な姿にやる気を感じました。
そしてついに当日。
手作りのお神輿を担いでぞう組(5歳児)が登場。「わっしょい、わっしょい」「そりゃあ、そりゃあ」とお神輿を上げ、たくましい姿を見せてくれました!「かっこいいー!」と、年下のお友達もじーっと見ていましたよ。
お店屋さんでは、ぞう組(5歳児)手作りのわなげ・おめん・魚釣り屋さんの店員になり「いらっしゃいませー」と、とても生き生きとした表情の子ども達でした♪年下のお友達も楽しそうにわなげや魚釣りをしたり、おめんを真剣に選んだりしていました。おめんをお楽しみ会中、ずっと頭に付けている子もいました。自分達が一生懸命作ったもので喜んでくれる姿を見るのは嬉しいですよね♪
その他にも、わにわにぱにっくやヨーヨー釣り、アイス・ポップコーン屋さんがあり、盛りだくさん!
ぞう組さん、計画や準備ありがとうー!!
磯遊び楽しかったね!
令和7年7月
くま組(4歳児)とぞう組(5歳児)が吉野保育所・金谷保育所のお友達と一緒に金谷海浜公園の磯へ遊びに行きました。楽しみにしていた子ども達。早速「きゃー!」「あったかーい」「気持ちいいー!」と言いながら喜んで海へ入って行きました。
足場が安定せず、「怖い・・」と言う子もいましたが、ウニやヤドカリを見つけると、大喜びで捕まえていました!「この下にも何かいるかな?」と石をひっくり返したり、海の中をジーっと見つめたり、海の中の生き物探しに夢中の子ども達でした。
保育者がウミウシを発見。恐る恐る触ってみると・・「ぷにぷにー!」と笑顔になるAちゃん。その姿を見て怖がっていたお友達も「ぼく(わたし)も触りたい!」と次々に触り、感触を楽しんでいました。お友達の存在ってすごいですね♪
初めはお互いにちょっぴり緊張している姿もありましたが、海へ入ると他の保育所のお友達とも自然と打ち解け、楽しんでいました。新しいお友達と一緒に夏ならではの貴重な体験ができました。
ザリガニ釣り
令和7年6月
うさぎ組(3歳児)・くま組(4歳児)が以前お散歩に出かけた時にくま組(4歳児)Aちゃんのおうちの近くのため池でザリガニを見つけました。「今度ザリガニ釣りに来ようね!」と話しながら帰ってきました。Aちゃんのおじいちゃんと地域の方のご協力でザリガニ釣りができることになりました。早速園庭で木の枝を拾って、自分たちで竿を作りました。「どれがいいかなぁ」「あった!」とお気に入りの枝を見つけて、タコ糸をぐるぐる巻きつけ完成!子どもも保育士も楽しみにしていました。
そして、待ちに待った当日。ちょっぴり長い道のりも頑張って歩き、ザリガニ釣りの場所に到着。「ザリガニいるかな?」と慎重にのぞきこみ、ザリガニの様子を観察します。
いよいよザリガニ釣りに挑戦!!「釣れるかなー」「あ、エサ食べた!」「あそこにもいるー!」と、みんな大興奮でした。子どもたちにとってはじーっと待つこともひと仕事ですが、子どもも保育士もみんなが夢中になり、大小さまざまなザリガニを釣り上げることができました。
たくさん釣れ、とても楽しいザリガニ釣りとなりました。釣ったザリガニは飼育するか逃がしてあげるか、話し合う機会を作ってくださるご家庭もありました。竿作りから始まり、釣り、命ある生きものとの向き合い方等さまざまな経験を通して、またひとつ成長した子どもたちです。
泥んこ遊び
令和7年5月
園庭に前日の雨でできた水たまりを発見。うさぎ組(3歳児)とくま組(4歳児)のお友達が早速泥んこ遊びを始めました。水が太陽の日差しで温まり、足を入れた瞬間「あったかーい!」と大喜び!ドロドロだったり、プルプルだったりする泥のさまざまな感触を手や足から目いっぱい楽しみました♪
そこへひよこ組(1歳児)とことり組(2歳児)のお友達もやってきて、仲間に入れてもらいます。水たまりに座り込み、全身泥だらけ!
汚れも気にせず夢中で遊びこみ、終始笑顔が楽しさを物語っていました。
泥んこ遊びは子どもの想像力や五感を刺激し、心身の発達を促す効果があると言われています。また思いきり遊ぶことでストレス発散になり、心が落ち着きリラックスできるようです。
これからもっと暑くなってくるので、泥んこや水遊びを思いきり楽しみたいと思います。
不思議な虹を見つけたよ!
令和7年4月
天気の良い日、うさぎ組(3歳児)・くま組(4歳児)とぞう組(5歳児)がそれぞれ違う場所に春を探しにお散歩に出かけました。田植えの様子を見せてもらったり、たんぽぽや藤の花が咲いているのを見つけたり、たくさんの春を発見してきました。
道端に生えている葉っぱも「くっつくかな?」と子どもたちにとってはあそび道具♪ぺたっとくっつき、嬉しそうでした。
そんな中、それぞれ場所は違うけれど、同じものを発見!!「見て!にじー!」と空を見上げると、なんと、太陽の周りにまるい虹を発見。
ぞう組(5歳児)は「虹と一緒に写真撮りたい」と大興奮。一緒に写真が撮れて、大満足の子どもたちでした♪普段見られない現象が見られ、素敵な散歩になりました。これからも機会を見逃さずに自然を満喫したいと思います。
(太陽や月の周りに現れる光の輪で、暈(かさ)や日暈(ひがさ)とも呼ばれる虹色現象のことをハロ現象と呼ぶそうです。)
3月も楽しかったー!!
令和7年3月
今月も楽しいことがたくさん!たくさんの思い出作りができました。
おわかれ会
「ぞう組さんにありがとうと伝えたい」「最後に楽しくあそびたい」という思いから、くま組(4歳児)が中心となって、うさぎ組(3歳児)とも相談しながらおわかれ会を開くことになりました。‟ぞう組さんには内緒“と、みんなで楽しめるあそびや思いを込めた歌、プレゼントの準備などをこっそりと進めていました。
おわかれ会大成功!!
おわかれ遠足(鴨川シーワールド)
ぞう組(5歳児)リクエストの鴨川シーワールド。シャチのショーのびしょ濡れコースを楽しんだり、かわいいイルカのショーを見たりと、楽しみました!
また、ぞう組はお買い物体験も行い、小学校で使う鉛筆を買いました。みんなおそろいの鉛筆をGETしてとても嬉しそうでした♡
ことり組(2歳児)ひよこ組(0,1歳児)の遠足
ぞう組(5歳児)くま組(4歳児)うさぎ組(3歳児)が、おわかれ遠足へ行き、お留守番だったことり・ひよこ組。天気が良かったこともあり、みんなで八雲神社へしゅっぱーつ!
こんなにたくさん歩けるようになりました♪
サッカー教室
ぞう組(5歳児)最後のサッカー教室も大盛り上がり!
最後に、コーチと一緒に給食も食べることができました。プレゼントも喜んでもらえて良かったね☆
コーチからは、『ナイスキッズ証』をいただきました!
ぞう組(5歳児)おわかれ遠足(マザー牧場)
竹岡保育所の年長児のお友だちと一緒に保育所最後のおわかれ遠足。乳しぼりをしたり、こぶたのレースを見たり、ソフトクリームを食べたりと最後の遠足を満喫してきました!I君、小学校でもよろしくね♪
ペコちゃんキャラバン隊が来たよー!
令和7年2月
2月21日(金曜日)、ペコちゃんキャラバン隊が保育所に来てくれました!
はじめに素敵なキャラバンカー「ペコちゃん号」とパシャリ☆
ホールで待っていると、ペコちゃんの登場です。
ちょっぴり緊張したのか、ギュッとお椅子を握る0歳児のお友だち。
でも、泣くことはなく次第に笑顔を見せ、ペコちゃんに釘付けでした♡
ペコちゃんクイズをしたり、『ペコちゃんの歌』のダンスを教えてもらって一緒に踊ったりと楽しみました。
2月がお誕生日のSくんもペコちゃんにお祝いしてもらいニコニコです♪
みんなもタッチしてもらったりギューしてもらったりと、楽しい時間を過ごしました。
最後にペコちゃんからプレゼントももらって、大喜びの子どもたちでした。
ペコちゃんキャラバン隊ありがとうございました!
初☆ピザづくり体験
令和7年1月
金谷にある『ピッツァ ゴンゾー本店』さんにて、竹岡保育所のお友だちと一緒にピザづくり体験をさせていただきました!
初めてのピザづくり体験をとても楽しみにしていた子どもたちです。
エプロン・三角巾・マスクをつけて準備はバッチリ!
はじめに、ピサ生地の伸ばし方のお手本を見せてもらいました。
「手は、こうかぁ…」と、しっかり見て真似ているぞう組(5歳児)。
さすがです。
生地を手で回すと、どんどん生地が伸びていき、薄く丸くなっていく様子に子どもたちも職員も「すごーい‼」と、感動です。
子どもたちも挑戦!
生地を薄くするところは、職員やお店の方に手伝ってもらい生地をみんなで伸ばしました。
「伸びたー!」と、嬉しそうです♪
生地ができたら、好きな具材を載せていきます。
「ベーコンにしよ!」「チーズいっぱいがいいかな☆」と、自分達でトッピングをしてニコニコです♪
そして、いよいよピザ窯へ!
順番に焼いてもらい、完成をドキドキ♡ワクワクしながら待っていました。
こんなにおいしそうな焼き立てピザができました!
「おいしーい!」と、夢中で頬張る子どもたち。
『ピッツァ ゴンゾー』さん、ありがとうございました!
「めっちゃおいしかったー!」と、満足気に保育所に戻ってきた子どもたち。
美味しいものを食べた後は、みんなで手を繋いで影で遊んだり、ぞう組(5歳児)M君のリクエストでドッジボールをしたりと、盛り上がりました!楽しかったね♪