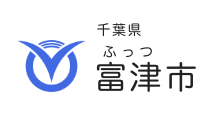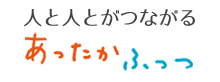あしあと
飯野保育所の保育風景
- 初版公開日:[2013年03月28日]
- 更新日:[2026年2月6日]
- ID:2348
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ページ内目次
日本の伝統行事とお正月遊び
令和8年1月
2026年、新たな年の訪れを祝い、一年の健康と幸せを願う伝統行事のお正月。保育所では13日に鏡開きを行ないました。由来について話をすると、真剣に耳を傾ける子ども達。なかには首をかしげる子もいましたが、鏡もちには年神様という神様がいることを伝えると、「ここに神様がいるの?」「すごい!」と一人ひとりが興味関心を深めていました。
神様からたくさんの力をもらい、元気に過ごせるよう皆で願いながら子ども達もトンカチでおもちを叩いてみました。「固いね。」「なかなか割れないよー!」「神様がいるから優しく叩いた方がいいかな?」などと話しながら順番に“トントントン♪”
しばらくしてようやくひびが入り割ることができると、子ども達は嬉しそうに拍手をし、割れたおもちを手でさわったり、固さを感じたりしていました。
誕生会では獅子舞が登場!赤い顔に大きな目、ギザギザの歯に長い体と、その迫力にびっくりする子、怖くて泣いてしまう子と反応はさまざまでしたが、太鼓のリズムに合わせて動く獅子舞に目を丸くしてじっと見つめていました。
獅子舞に頭を噛んでもらうと、“病気をせず元気に過ごせること、悪いものから守ってくれること”という話を聞いた子ども達。
少し怖さはあるけれど、勇気を出してそっと頭を噛んでもらいました。獅子舞の大きな口にドキドキしながらも「できた!」というホッとした表情や達成感を感じられたようです。こうして伝統行事にふれることは、子ども達にとって特別な体験となります。今後も日本の文化に親しむ機会を作っていきたいと思います。
お正月遊びも楽しんでいます。なかでも、いるか・うさぎ・ぱんだ組(3・4・5歳児)はコマ回しに夢中です。
初めはヒモの巻き方、投げ方に苦戦し、「難しい」「できない」「面白くない」と弱音を吐く子もいましたが、諦めずに頑張れたのは、"できるようになりたい"という強い思いがあったからです。
お友達同士で励まし合いながら根気よく練習をすると、今では上手に回せる子が増え、さらに手の平にのせて回すワザに挑戦するなど、皆で競争をしながら真剣勝負を繰り広げています。
りす組(2歳児)はカルタ遊びで盛り上がっています。初めてのカルタもルールをすぐに覚え、2回目3回目と回を重ねるごとに2歳児とは思えない白熱した戦いに!
最近は子ども達が簡単な読み札を読み上げることもできるようになり、遊びを通しての成長も見られました。
ちょうちょ組(0・1歳児)は、わらべうた『ぺったらぺったん』がお気に入り。「もう一回!」とリクエストが続き、繰り返し楽しんでいます。お手玉をおもちに見立てて「ぺったらぺったん、もちつけもちつけ・・・♪」と子ども達も口ずさみ、最後はお手玉を頭の上に乗せます。
遊びの中で見せてくれる一人ひとりの表情やしぐさがとても可愛らしく、上手に表現をしている子ども達です。
クッキング

令和7年12月
今年は保育所の畑だけでなく、ご近所の飯野ラーメンさんのご厚意でさつま芋掘りをさせて頂きました。広い芋畑に目を輝かせながらみんなで力を合わせて『うんとこしょ どっこいしょ♪』
大きくて立派なさつま芋をたくさん掘ることができました。
そして後日、楽しみにしていた焼き芋会を行ないました。
さつま芋についている土をきれいに落としながら“美味しいお芋になりますように☆”とわくわくした表情で準備をするいるか組(3歳児)。『僕のお芋、クルクルまきまき上手に出来たよ!』と得意顔のAくん。お芋がこげないようにしっかりと包みます。
園庭では火起こしが始まると、興味津々の子ども達。途中で火が弱まると、急いで枯れ葉や木の枝を集めに行くぱんだ組(5歳児)。その姿を見た年下のお友達も進んでお手伝い。
やがて火の広がりに気付いたり、両手をかざして温かさを感じたり、燃える音に耳を傾けるなど、お友達同士で嬉しそうに話しながら焼き芋会の雰囲気を味わい、あつあつホクホクのお芋を頂きました。
別の日には、りす・いるか・うさぎ組(2・3・4歳児)が“さつま芋チップス”を作りました。スライサーを使うと、大きかったお芋があっという間に薄くスライスされ、子ども達はびっくり!また、いろいろな種類のお芋を使用したので、『黄色だね』『こっちはちょっとオレンジだ!』と見比べ、完成すると『サクサクしてるね。』『甘くて美味しい!』と調理を通して気付く面白さを感じられたようです。
うさぎ組は自分達で育てている大根を収穫。根元をしっかりと持ち、力を込めてスポン!上手に抜くことができました。
大きく育った大根は丁寧に洗い、包丁で切って塩漬けに。シンプルな味付けですが、採れたての大根本来の味を感じることができ、子ども達は大好きです。
ぱんだ組は“スイートポテト”作りをしました。これまでのクッキングでの経験を活かして、皮むきや切る作業、マッシャーでつぶして形作りをするなど、一つひとつの工程をしっかりとこなす姿はさすが年長さんです。
みんなで楽しみながら美味しいスイートポテトを作ることができました。
そして最後は、今回お世話になった飯野ラーメンさんへ、子ども達が作ったスイートポテトと芋ヅルを巻いて作ったクリスマスリースをお届けに行きました。
『さつま芋をくれてありがとうございました!』と感謝の気持ちをお伝えすると、喜んで受け取って下さり子ども達も嬉しそうでした。
こうして日頃から保育所での活動を地域の方々に見守って頂いているおかげで、今回の交流につながりました。
今後も地域の方とのふれ合いやつながりを大切にしていきたいと思います。
うんとこしょ どっこいしょ!

令和7年11月
りす組(2歳児)のお友達は、【絵本】「大きなかぶ」のお話が大好きです。ここまで興味をもったきっかけは、一枚のお口拭きタオルでした。
遡ること5月のある日。テーブルの上にポツンと置いてあったタオルを見つけた保育士。(ここで一つの遊びを思い付きました。)
「これ誰の?」『これ僕のー!』といつもの何気ない場面で始まったお口拭きタオルを使っての引っ張り合いっこ。「一人じゃ先生に勝てないね。どうする?」と子ども達になげかけ、さらに「おーい、誰か手伝ってくれー!」と声をかけてみました。すると、まわりのお友達が集まり、あっという間に長い列が出来ました。それから数日このやりとりをしていると、いつの間にか楽しい遊びへと変わっていったのです。

また別の日の出来事。りす組の畑に植えたさつま芋が大きく育ちました。生長を見守っていた子ども達。ある時、Aちゃんがツルを見つけて手を伸ばすと、ここでも『うんとこしょ、どっこいしょ』と言う可愛い声とともにお芋掘りが始まりました。
11月下旬頃には、今年も昨年に続いて、ご近所の飯野ラーメンさんのご厚意でさつま芋掘りをさせて頂きました。りす組さんは行く前から、『うんとこしょ どっこいしょするー♡』と大喜び!当日は広い芋畑に目を輝かせ、『たくさん掘るぞー!』と腕まくりをしてお芋掘りスタート。
フカフカの土にふれながら『どこかなー?』と夢中になって探します。まるで宝探しをしているかのようです。
どんどん掘っていくと、『あったー!』と嬉しそうな声が。掘れば掘るほど出てくるお芋に大興奮の子ども達です。
でもなかにはすぐに出てくれないお芋も。すると、『おーい誰かー、手伝ってくれー!』
大きなかぶならぬ大きな芋にチャレンジです。その声に“待ってました”とばかりにお友達が集まってきます。みんなで力を合わせて『うんとこしょ どっこいしょ!うんとこしょ どっこいしょ!!』
そして・・・、すっぽーん!!
おもわず後ろにいたお友達が次々に尻もちをついてしまうというハプニングもありましたが、それよりも大きくて立派なお芋を掘ることができた嬉しさをみんなで味わえたことに笑顔いっぱいの子ども達。まさに絵本と同じ光景ですね。
『わぁー、抜けたー!』『やったー!!』『おもたーい!』と賑やかな歓声が響き渡っていました。
一生懸命に掘った手は、土でまっくろくろ!それをみたりす組さんは、『ふふっ♡』と誇らしげな表情です。頑張った証拠ですね。
絵本の世界だけでなく、こうして実際の体験を通してたっぷりと楽しむことができました。12月には生活発表会があります。もちろんりす組は、「おおきなかぶ」のお話で劇遊びを行います!
お友達といっしょは楽しいね!
令和7年10月
ちょうちょ組(0・1歳児)は、毎日元気いっぱいに過ごしています。最近はお友達とのやりとりも多く見られ、さまざまな遊びを楽しんでいます。
ポカポカ陽気の日は大好きな外遊びへ。“早く行きたい!”と待ちきれない1歳児のお友達は、自分達で帽子を被ったり靴下を履こうとしたりと、はりきって準備をします。
園庭に出ると、それぞれ好きな遊びへ一直線!AちゃんとB君は、鉄棒にぶら下がるのが上手です。小さい手でしっかりと握り、足を曲げてぶらーん!『すごいでしょ?』と得意顔です。
赤いお船はお気に入りの場所。ここでは、0歳児のCちゃんが仲間入りです。みんなで向かい合っておしゃべりをしたり、ユラユラ揺らしてみたりとお友達同士の楽しい空間になっています。
ぱんだ組(5歳児)が、運動会に向けてチャレンジしている板登りに気付くと自然と遊びの手が止まり、保育士と一緒に熱い視線を送ります。そしてかっこよく登る姿に『おぉー!!』と拍手をして応援。憧れのお兄さんお姉さん達の姿に目を奪われていました。
室内では牛乳パックで作った台を橋のように並べると、お友達が次々に集まってきます。春先の頃に比べて子ども達の足元は安定し、バランスをとりながら渡ったり、両足でジャンプをしたりとお手のもの。運動遊びも大好きです。
こちらはビリビリチラシ遊び。クシャクシャと丸める子、ビリビリ細かくちぎる子、それぞれが夢中になって遊びます。ちぎった紙を牛乳パックに入れるDちゃん。たくさん集まると、『いっぱいだよ!』と嬉しそうに教えてくれました。保育士が花吹雪のようにヒラヒラと降らせると、子ども達は期待に満ちた表情で、『キャー!』『もっかい(もう1回)』と大喜び。保育士と遊んだ後は、お友達同士でも頭の上にヒラヒラー♪そして、お互いの顔を見てはニッコリ♡言葉は多くなくても“楽しいね”という気持ちがしっかりと通じ合っています。
そんな楽しそうな光景に0歳児のF君も興味津々。チラシに手を伸ばしてじっと見つめながら感触を確かめます。さらに1歳児のお友達を真似て、上手にギュッギュッと丸めていました。
わらべうた遊びも大好きな子ども達。“どんぐりころちゃん”では、歌に合わせて保育士の手に隠れた本物のどんぐりを見つけます。『どっちの手にあるかな?』と毎回真剣な表情で注目!身を乗り出して『こっち!』『あったー!』とみんなで当てっこをしながら盛り上がりを見せています。
好きな遊びを楽しむ中でお友達との関係も深まり、積極的にやりとりをする姿が増えてきたちょうちょ組さん。これからもお友達と気持ちを共有する喜びや楽しさを感じられるように関わっていきたいと思います。
ごっこ遊び楽しいな【八百屋さん開店パート(2)】
令和7年9月
※パート(1)は、8月のホームページをご覧ください。
先月から楽しんでいたごっこ遊びが広がり、いよいようさぎ組(4歳児)がこの日のために準備を進めてきた八百屋さんの本番を迎えます。
始まる前にみんなでお店屋さんの最終確認をしました。その中で、『ドキドキするね』『上手にできるかな?』と不安もありましたが、それ以上に楽しみな気持ちの方が大きく、期待に胸を膨らませているうさぎ組です。確認のあとは、手作りの野菜のお面とエプロンを身につけて八百屋さんに変身です。
たくさんのお友達(お客さん)を前に、最初は「やおやのおみせ♪」の手遊びからスタート!お店屋さんになりきる子ども達は、いきいきとした表情で笑顔いっぱいです。
そして、待ちにまった八百屋さんの開店です。テーブルの上には新鮮お野菜(きゅうり・トマト・なす・スイカ)がずらりと並びます。『いらっしゃいませー!いらっしゃいませー!』という掛け声でやってきたのは、0・1・2歳児のお友達。『どれがいいですか?』『野菜は1つ選んでね!』『お金もくださーい!』と自然とリードしてくれる八百屋さんです。また、視線を合わせて一緒に選んでくれる優しい姿も見られました。おかげで、年下のお友達は楽しくお買い物ができ、買ったお野菜を大事に持ち歩いていましたよ。
さて、続いてはいるか組(3歳児)ぱんだ組(5歳児)のお友達が来店です。たくさんのお野菜を前に『どれにしようかな?』と目移りしたり、一つひとつに目を向け、『おいしそうな野菜はこれかな?』と吟味したりするなど時間をかけてお好みのものを探しています。悩んでいるお客さんには、『これがおいしいですよ!』『とっても甘くてびっくりしちゃいます!』とおススメをすることも忘れないうさぎ組のみんな。
最初は緊張していたのが嘘のように堂々とした立ち振る舞いです。その姿はまるで本物の八百屋さんのようで、上手なやりとりをしていました。
一方で、お客さんが少なくなってきたトマト屋さん。どうしようかと考えた結果、『いらっしゃいませー!』『まだまだおいしいトマトがいっぱいありますよー!!』と自分達で工夫をして、元気いっぱいの呼び込みを開始。おかげでお客さんが来てくれ大喜びでした。
楽しい時間はあっという間に過ぎていき、最後は『これで八百屋さんは閉店です!』と看板を出して終了しました。“閉店”という看板を出すのは、うさぎ組のアイデアです。
そしてもう一つ。園外保育へ出掛ける時にいつもお世話になっている“ふっつんバス”。子ども達も大好きです。そこで考えたうさぎ組さん。八百屋さんの次は運転手さんになって、今日来てくれたお客さんをクラスまで送ってくれる嬉しいサービスを行なってくれました。
この日までの活動一つひとつを楽しんできた子ども達。また、初めてみんなでやり遂げた満足感を味わい、自信につながったと思います。お店屋さん大成功!
ごっこ遊び楽しいな!【パート1】
令和7年8月
7月に行なった夏のお楽しみ会で、ぱんだ組(5歳児)が手作りの鋸山を作ってみんなを楽しませてくれました。参加したうさぎ組(4歳児)は、『ぱんだ組さんすごいね!』『どうやって作ったの?』『またやりたいなー!』と大興奮。ぱんだ組への憧れの気持ちが強くなったようです。それと同時に、『僕達(私達)も何か作ってみたい!』という意欲が高まっているようでした。
みんなで盛り上がりを見せていたちょうどその頃。うさぎ組の畑でお世話をしていたきゅうりを収穫し、採れたてを美味しく食べたという経験から、『きゅうり屋さんやりたい!』という声が上がりました。
それをきっかけにお店屋さんごっこがスタート。早速段ボールで作ることにしました。ハサミでチョキチョキと夢中になって切ります。
1つ2つと出来上がるたびにわくわくでいっぱい!いよいよ完成です。
『いらっしゃいませ!』『きゅうり屋さんですよー!』とお店屋さんを楽しんでいると、その姿を見た他の子達も興味津々。
いつのまにか、お友達からお友達へ遊びの輪が広がり、やがてクラスのみんなで1つの遊びを楽しむようになりました。
そんな光景を見た保育士は、9月の誕生会でお店屋さんをやるのはどうかと提案しました。すると子ども達は『やりたい!』と大喜び。その後の話し合いでは、誕生日のお友達や小さい組さん、さらにお楽しみ会で楽しませてくれたぱんだ組さんを招待すること、そしてお店屋さんは、きゅうりだけでなく『ミニトマトやナス、スイカも売りたい!』などの意見も出ました。
少しずつイメージしたものが形になっていく嬉しさを味わっているうさぎ組。“きゅうり屋さん”から始まったごっこ遊びは、“八百屋さん”になり、今度はクラスの垣根を越えて、みんなで楽しもうということになりました。
現在も準備の真っ最中です!子ども達は『1つずつハサミで切って野菜を作りたい』という思いが強く、自分達でアイデアを出し合いながら牛乳パックに絵を描いて、ハサミで切る作業に取り組んでいます。お客さんに買いに来てもらうためにはたくさんの野菜が必要です。
準備は大変ですが、楽しい気持ちが上回っている子ども達は、『大きなナスを作るんだ!』『スイカ美味しそうに作れたでしょ?!』『見て、上手に切れたよー!』と素敵な表情をたくさん見せてくれます。おかげでハサミの使い方も上手になりました。
少しずつ増えていく野菜を並べ、『もう少しで八百屋さんができるね!』とおもわず笑みがこぼれるうさぎ組です。
また、『お店屋さんにはお金もないとダメだね!』とペットボトルのキャップに10・50・100・500円と書いて作りました。
八百屋さん開店まであと少し!みんなで力を合わせて頑張るぞー!!
お楽しみ会楽しかったね!
令和7年7月
夏のお楽しみ会に向けて、今年はどんなことをやろうかと話し合いを進めてきたぱんだ組(5歳児)。その中で出てきたのが、5月に園外保育で出掛けた“鋸山”でした。
子ども達にとって初めて登った鋸山は大変で疲れたけれど、それ以上に楽しい思い出となっていたことから、『次は(年下の)お友達にも教えてあげたい!』という意見でまとまりました。それをきっかけにぱんだ組のお部屋を鋸山に変身させることに決定したのです。
当日までお友達には内緒にしたいということで、毎日こっそりと準備をしてきた子ども達です。
そして、まちに待ったお楽しみ会の日を迎えました。まずは手作りのロープウェーでお友達を迎えに行きます。切符をもらったらいよいよ出発!
到着までの間は、案内役のぱんだ組がエスコート。『次はいるかぐみー♪』『しっかりつかまってくださーい!』と声かけがとても上手です。
また、窓から風が入ると、『風が吹いているので気を付けてくださーい!』とまるで本物のガイドさんのようにお客さんの安全を守りながら、行き帰りの旅を盛り上げてくれました。
ついに鋸山へ到着!
切り通しトンネルや地獄のぞき、百尺観音などを表現した各名所が盛りだくさん!そこにはぱんだ組のアイデアを取り入れた虫とりやヨーヨー釣り、輪投げ、玉入れと楽しいゲームもあり、一つひとつ工夫を凝らして作った素敵な鋸山は見どころ満載です。
あっという間にたくさんのお客さんでいっぱいになりました。
ぱんだ組はお店屋さんになってお友達をしっかりサポートします。『次はこっちに来てくださーい!』『このゲームはこうやってやるんだよ!』と積極的に呼び込みをしたり、優しく手を引いて案内をしたりと大忙し!それでもみんなが笑顔で楽しむ姿を見ると嬉しくて、お店屋さんのお仕事にも自然と力が入ります。
ちょうちょ組(0・1歳児)のお友達にはどうやってお話をしたらよいか難しさも感じたようですが、身振り手振りで寄り添いながらリードしてくれました。さすが頼りになる年長さんです!
楽しいひとときはあっという間に終わりを迎えます。名残惜しさを感じつつも、『喜んでくれてよかった!』『お友達がもっと遊びたいって言ってくれたから嬉しかった!』と満足感や自分達で力を合わせてやり遂げたという達成感をたくさん味わうことができたぱんだ組。
また一つ心に残るお楽しみ会となりました。
かわいいお客さま
令和7年6月
ある日のこと。職員室前のプランターの花に水やりをする所長先生。その時、いつもとは違う光景がありました。よく見るとそこには鳥の巣があり、小さな卵もあったのです。
子ども達に知らせると、目を輝かせて覗き込みます。この日は土曜日で限られた子達しか見ることができませんでしたが、休み明けにはすぐに子ども達からお友達へ、瞬く間に話は広まっていきました。
この日から毎日時間を見つけては入れ替わり立ち代わり、みんなで巣を観察。こんなに間近で見ることは初めてだったので、わいわい賑やかな声とともに大興奮です。
そんな中、少し離れたところからこちらを見つめる一羽の鳥を発見!『そういえば最近近くにいるよね。』という会話から、やがて『卵のお母さんはあの鳥だ!!』と気付いたのです。
お母さん鳥は、子どもが集まってくると驚いて逃げてしまいます。そこで観察をする時は、足音を立てずにそっと…。大きな声を出すお友達がいると、『静かにしないとびっくりしちゃうよ。』『お母さん鳥が巣(お家)に戻ってこれるように少し離れて見ようよ!』『卵の赤ちゃんもママがいなくて泣いてるかも』などとお母さん鳥を思いやる言葉が多く聞かれるようになりました。
そんなお兄さんお姉さんの声に年下のお友達も『かわいそうだね。』『しー(静かに)だね。』と気持ちを共有し、寄り添っていました。
卵の赤ちゃんだけでなく、お母さん鳥にも興味津々の子ども達。図鑑で調べると、“ハクセキレイ”という種類の鳥であること、そして幸運の象徴と言われていることがわかりました。
卵を大切に温め続けるお母さん鳥。
それから数日後、ついに卵から孵化したヒナ五羽が順に生まれました!『赤ちゃんだー!』『小さくてかわいい!』『体の色はピンク色なんだね。』『一生懸命に動いてる!』と子ども達は大喜び。嬉しい気持ちをみんなで伝え合いながら眺めていました。
卵を温めていた時は一羽だったハクセキレイも、ヒナが生まれると二羽に。ここからはお父さんハクセキレイも子育てに参加していました。
さらにこの頃になると、保護者の方々にも話は広がり、送迎時は子ども達が保護者の手を引いて来ます。『今日も元気かな?』『大きくなったかな?』『お口パクパクしてるよ!』と一緒に観察。毎日みんなで成長を見守り、すっかり飯野保育所の話題の中心となっていました。
これからも大きく育っていく姿をずっと見たいと思っていた矢先の出来事…。
いつものように巣を見ると、突然ヒナがいなくなっていたのです。これに気付いた子ども達はびっくり。すぐにその場の状況を飲み込めずにいました。職員の中ではカラスに食べられてしまったのではないかと予想しましたが、子ども達からは『自分でごはんが食べられるようになって(エサを)探しにいったんじゃない?』『お母さん(鳥)とお出かけしたんだよ!』と話す声も聞かれました。
巣は現在もそのまま残しています。
以前と変わらず子ども達は巣の様子を見に来たり、空を見上げたりしています。
『もしかしたら…』という思いもあり、『いないねー。』『いつ帰ってくるかな?』とまた会える日を楽しみにしています。
目指せ、鋸山!
令和7年5月
ぱんだ組(5歳児)に進級して初めて行く園外保育の日を迎えました。行き先は鋸山です。
4月に出掛けたお散歩で、ふと『お山にトトロっているのかな?』という話からさらにやりとりは続き、担任との会話で鋸山についての話題になりました。そこからみんなで行ってみたいねという気持ちが高まり決定しました。
そして当日。まずはロープウェーに乗ります。改札で一人ずつ切符を切ってもらい、ホームに出るとロープウェーがお出迎え。この日、園外保育の話を聞いて金谷保育所のお友達がお見送りに来てくれました。
『いってきまーす!』『いってらっしゃーい!』と手を振り、わくわくドキドキみんなを乗せたロープウェーはどんどん高く上がっていきます。
自然と手すりをつかむ手には力が入り、『怖い…』というお友達もいましたが、景色が見えてくると『あっ、金谷のお友達がどんどん小さくなっていく!』『海も見えるよ!』と嬉しそうに歓声を上げながら空の旅を楽しんでいました。
ロープウェーを降りたあとは、急な階段の登り降りが続いていきます。普段の散歩道とは違い、デコボコとした石の階段は歩きにくく、また、雨上がりで地面はすべりやすくなっていたので、子ども達にとっては大変です。
それでも一歩ずつ足を進めていくうちにだんだんと『こっちから行った方が歩きやすい!』と意欲を見せたり、『ここ(手すり)につかまっていくと怖くないよ!』『大丈夫?気をつけてね!』とお友達同士で励まし合ったり、それぞれが自分のペースでしっかりと歩けるようになりました。
しばらくすると巨大な崖の隙間が現れ、そこを抜けると大人だけでなく、子ども達も肌で感じるほどの空気感。
その先に見えたのは“百尺観音”です。石切場跡に彫られた観音様におもわず言葉を失います。圧倒される大きさと神秘的な姿に目を奪われていました。
次は山頂にそびえ立つ“地獄のぞき”です。地獄という言葉に興味津々の子ども達。最初は余裕のある表情を見せていましたが、いざ上に登ると怖さが倍増!勇気を出して断崖絶壁から下を覗き、絶景を目に焼き付けます。遠く離れたカメラマンの保育士を見つけると、『怖ーい』と言いながらも大きく手を振ってポーズ!貴重な体験ができました。
石のトンネルを抜け、木々に囲まれた場所では『素敵だね!』『あの木は何ていう木かな?』と目に入る景色から感じたことを話す子ども達もいました。また、『どんぐりが落ちてないからトトロはいないかなー?』『おーい、トトロ出て来てー!』と呼びかける可愛らしい会話も。お話の世界に入り、その場の素敵な雰囲気を存分に味わう姿が見られました。
最後は大仏広場に到着。日本一大きく迫力満点の大仏様に子ども達は大喜びです。
帰り道では強風からロープウェーが止まってしまうかもしれないというハプニングがあり、ハラハラドキドキしましたが、無事に下山することができました。
『いっぱい歩いて疲れたけど楽しかった!』『色んな景色が最高だった!』と一人ひとりの表情は達成感であふれています。鋸山楽しかったね!
春を見つけに行こう!
令和7年4月
ポカポカ陽気が気持ち良いある日。うさぎ組(4歳児)は春を探しにお散歩へ出かけました。戸外へ出ると、「今日はあったかいね!」「お日さまが出てるからね!」と空を見上げ、両手を伸ばして暖かい日差しを体いっぱいに受け止める子ども達。これからの活動に胸を弾ませながら「行ってきまーす!」と元気に出発です。
真っすぐに伸びる田んぼ道を歩いていると、たんぽぽを見つけたA君。「このたんぽぽ大きい!」「いいにおいがするよ!」と指先でさわったり、においをかいだりして嬉しそうに摘むと、カメラの前でハイポーズ!
BちゃんとCちゃんは、ヨシの葉っぱで草笛作り。音が鳴る・鳴らない面白さや不思議さを感じたり、その他にも音の違いに気付いたりするなど、2人で演奏会を楽しんでいました。
春の自然探しでは、大人が気付かない視点でいろいろなものを見つける子ども達。その中で、「これ何だろう?」と細長い葉がたくさん集まった野草を発見しました。保育士から、これは『ノビル』であること、食べられることを教えてもらうとびっくり!そこから一気に興味が広がったうさぎ組です。
この日は雨上がりだったこともあり、土が柔らかく、子ども達の力でも次々と抜くことができました。スポーンと抜けるのが気持ち良く、「もっといっぱい採ろう!」「見て見て、こんなにたくさん採れた!」と夢中になって収穫。
長い葉っぱの先端には丸い玉のようなものがあります。「固いね。」「玉ねぎのにおいがするよ!」と感じたことはみんなで顔を寄せ合って確認!何か発見があるたびにこうして集まって共有するのも楽しみの1つです。
たくさん収穫した『ノビル』は、みんなで食べてみようということになりました。
そして、次の日はクッキングです♪
水できれいに洗ってお鍋でグツグツ茹でます。だんだんと「においがしてきたね。」「早く食べてみたい!」とわくわくする子ども達。完成したノビルはマヨネーズで和えて食べました。お味はどうかな??
大人でもちょっと辛く感じる味ですが、「シャキシャキして美味しい!」「もっと食べる!」と大人気。
なかには、少しかじって「苦手・・・。」と残してしまう子もいましたが、「ノビルってこんな味がするんだ。知らなかったー!」と初めて経験できたことに嬉しさを感じるお友達もいました。
次はどんな自然遊びができるのか楽しみです。
ぱんだ組さんありがとう!
令和7年3月
ある日、うさぎ組(4歳児)が遊んでいると、ぱんだ組(5歳児)の部屋から素敵な歌声が聞こえてきました。卒園式に向けて歌の練習をしていることを知った子ども達は、「ぱんだ組さんが卒園しちゃうの寂しいね。」「小学校に行っちゃうのか…。」といよいよお別れが近づいていることを感じ、ぱんだ組の話題でもちきりです。
そこから「ぱんだ組さんが喜ぶことをしたい!」「みんなでありがとうを伝えよう!」と“お別れ会”を計画することになりました。
早速みんなで話し合いをしますが、最初は何をしたらよいのか悩む子ども達。そこで、保育士が卒園式のテーマが“海”
であることを伝えると、何やらひらめいたようです!
「じゃあお別れ会も海にしちゃおうよ!」「もう一回海のダンスパーティーの劇をやろうよ!」と即答でした。
なぜテーマが海なのか…。
今年のぱんだ組は海に親しむ機会が多くあり、一人ひとりの楽しい思い出になっているという経緯があったからです。
そしてもう一つの『海のダンスパーティー』について。
これは、うさぎ組が発表会で行なったオリジナルの劇です。ぱんだ組と同じようにうさぎ組もさまざまな活動を通して海が大好きになったので、今回は思い出の劇をアレンジしたお別れ会バージョンを披露することにしました。
さらに、「プレゼントもあげよう!」という思いから、「小学校に行っても使える物がいいよね!」「僕のお兄ちゃん、鉛筆を入れる箱を使ってるよ!」とどんどん意見が出てきます。そして決まったのが鉛筆立てです。海をイメージしてシーグラスを飾ろうという素敵なアイディアも生まれ、メッセージカードも一生懸命書きました。ぱんだ組さんの喜ぶ顔を思い浮かべると、わくわく嬉しくなり、楽しんで取り組むことができました。
ここまでの準備をぱんだ組に内緒で行なってきたうさぎ組ですが、「それだと、お別れ会に来てくれないかも…。」と心配になり、招待状を作ることにしました。
完成すると、早速みんなでぱんだ組へ渡しに行きました。
いよいよお別れ会当日。「喜んでくれるかなー?」「ドキドキする。」と話していたうさぎ組。少し戸惑いはありつつも次は自分達がぱんだ組になるんだ!という気持ちが芽生えているので、それが一人ひとりの頑張る力に繋がっています。
ぱんだ組さんを迎え、海のダンスパーティーがスタート♪ここでは、ぱんだ組さんとの思い出を振り返ったり、一緒にダンスを踊ったりと大盛り上がり!
この光景にちょうちょ組(1歳児)のお友達も両手を広げて満面の笑みです。
心を込めて作ったプレゼントは、渡す直前まで後ろに隠す徹底ぶり。最後までびっくりさせようとサプライズを忘れない子ども達の姿がとても可愛らしかったです。
受け取ったぱんだ組さんが「ありがとう!」と言ってくれると嬉しくて、「喜んでくれた!よかったー!」とホッと一安心の子ども達でした。
ぱんだ組さんからは、お返しに折り紙で作った素敵なお便りホルダーをもらいました。
最後までみんなの「ありがとう」の気持ちがたくさんつまったお別れ会は大成功!何より、ここまで先頭に立って準備を進めてきたうさぎ組のお友達は、ぱんだ組さんが楽しむ姿を見て自然と笑顔に。自分達でやり遂げた達成感を味わうことができました。
ぱんだ組さん、小学校に行っても元気でね!
お別れ遠足
令和7年2月
もうすぐ卒園を迎えるぱんだ組(5歳児)とのお別れ遠足(マザー牧場)の日がやってきました。当日はお天気にも恵まれ、子ども達は「みんなで遠足に行けるから嬉しい!」と大喜び。「行ってきまーす!」と元気に出発しました。
いるか組(3歳児)はバスに乗って遠足に行くのが初めてということもあり、ウキウキわくわくなこの表情です。窓から景色を眺めたり、おしゃべりに花を咲かせたりと車内はとても賑やかでした。
いよいよ到着!バスを降りて最初にみんなを出迎えてくれたのは、澄んだ青空に浮かぶ富士山。「大きいねー!」「きれいだねー!」と一斉に喜び合っていました。
マザー牧場で最初に出会った羊。側へ駆け寄ると、囲いの中からひょっこり顔を覗かせ「はじめまして」とご挨拶。ちょっとびっくりするAちゃんでしたが、「おくちモグモグしてるよ。可愛いね。」と保育士に伝えてくれました。
うさぎ組(4歳児)は、『赤ちゃん羊成長館』へ行き、これまでに生まれた赤ちゃん羊の写真を見ました。残念ながら本物の赤ちゃん羊はいませんでしたが、お腹の大きいお母さん羊に会うことができました。
そして、ここでは楽しいクイズに挑戦!
子ども達がもつ素敵な発想力で積極的に答える子が多く、大盛り上がりでした。
広場を歩いていると、偶然小屋に戻る大きな馬に会いました。その時、お友達はよーく耳を澄ませます。足音を聞いた瞬間、「お馬って本当にパカッパカッって音がするんだ!」とびっくり。
そしてその音の正体が、馬の『蹄鉄(ていてつ)』だということも教えてもらいました。子ども達は、知らなかったことを知れた嬉しさや新たな発見に、さらなる関心が深まったようです。
人気のシープショーでは、子ども達の目がくぎづけ!
ふれあいタイムになると、「黒いお顔の羊もいるんだね!」「羊の角ってこんな形なんだ!」「羊の毛ってふわふわしてる!」といろいろな角度からじっくりと観察し、興味津々。細かい特徴にもよく気付いて、お友達や保育士と楽しそうに話してました。
ぽかぽか陽気の中でお弁当タイム!お待ちかねのソフトクリームも美味しくいただきました。
次にやってきたのは、大人気のこぶたのレース。ここでは、参加希望のお友達がたくさんいましたが、見事抽選に当たったお友達は大喜びです。
こぶたの中には、なかなか言うことを聞いてくれなかったり、突然動かなくなってしまったりすることもありましたが、優しく誘導しながらお尻をペンペン。なんと3レースとも飯野保育所のお友達が優勝でした!
牛の乳しぼりでは、難しさがありましたが、保育士の手助けなく上手にしぼることができました。「牛さん、可愛かった!」「牛のおっぱいって温かいんだね。」と間近で牛のぬくもりを感じられたことに嬉しさでいっぱいのようでした。
他にもうさぎやモルモット、リクガメ、カピバラなど、たくさんの動物とふれあうことができた子ども達。貴重な体験を通して、動物への興味はさらに広がり、ぱんだ組のお友達との楽しい思い出もたくさんできました。
お問い合わせ
電話・ファクス: 0439-87-0765