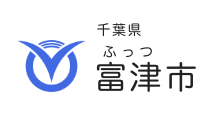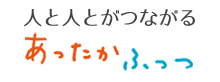あしあと
介護保険料
- 初版公開日:[2011年01月13日]
- 更新日:[2025年7月22日]
- ID:124
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護保険料
介護保険は、40歳以上の皆さんに納めていただく介護保険料と公費(国・県・市)を財源として、介護が必要となった方が、安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支える制度です。誰もが安心してサービスを利用できるよう、介護保険料は必ず納めましょう。
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、下表のとおり所得に応じ13段階に区分し、それぞれの保険料額を負担します。富津市における基準保険料額は、年額80,400円(月額6,700円)です。
なお、第1段階から第3段階の方については、保険料負担額の軽減を行った後の金額となっています。
| 保険料段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者または市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者、若しくは市民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80.9万円以下の人 | 基準額×0.285 | 22,910円 |
| 第2段階 | 市民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80.9万円を超え、120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 38,990円 |
| 第3段階 | 市民税非課税世帯で、第1段階及び第2段階の要件に該当しない人 | 基準額×0.685 | 55,070円 |
| 第4段階 | 市民税課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80.9万円以下の市民税非課税者 | 基準額×0.900 | 72,360円 |
| 第5段階 | 市民税課税世帯で、第4段階の要件に該当しない市民税非課税者 | 基準額×1.000 | 80,400円 |
| 第6段階 | 前年の合計所得金額が120万円未満の市民税課税者 | 基準額×1.200 | 96,480円 |
| 第7段階 | 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の市民税課税者 | 基準額×1.300 | 104,520円 |
| 第8段階 | 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の市民税課税者 | 基準額×1.500 | 120,600円 |
| 第9段階 | 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の市民税課税者 | 基準額×1.700 | 136,680円 |
| 第10段階 | 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の市民税課税者 | 基準額×1.900 | 152,760円 |
| 第11段階 | 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の市民税課税者 | 基準額×2.100 | 168,840円 |
| 第12段階 | 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の市民税課税者 | 基準額×2.300 | 184,920円 |
| 第13段階 | 前年の合計所得金額が720万円以上の市民税課税者 | 基準額×2.400 | 192,960円 |
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険の算定方式により決まり、健康保険料とあわせて納めていただきます。
介護保険料の納め方
介護保険料の納め方は、年金の受給額等により『普通徴収』と『特別徴収』に分かれます。
普通徴収
老齢・退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円未満の人や、65歳になった人、富津市へ転入したきた人は年金天引きが始まるまで、納付書や口座振替で納めていただきます。
| 納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期限 | 7月31日 | 9月1日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月1日 | 1月5日 | 2月2日 | 3月2日 |
コンビニ等で納めることができます
納期限内であれば、介護保険料をコンビニエンスストアやスマホ決済アプリで納めることができます。
- コンビニエンスストアでの納付
全国のコンビニエンスストア店舗等で納めることができます。納付できる店舗等は、納付書の裏面に記載している「納付場所」を確認ください。 - スマホ決済アプリでの納付
「au PAY」 「d払い」 「Fami Pay」 「PayB」 「PayPay」なら、納付書のバーコードを読み取るだけで24時間いつでも、どこでも納付できます。
※事前にアプリ内から利用登録等をする必要があります。
特別徴収
老齢・退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上の人は、原則として年6回の年金の定期支払の際に介護保険料天引きされます。
(老齢福祉年金、寡婦年金及び恩給は、特別徴収の対象となりません。)
仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年の所得が確定していないため、通常は、前年度2月の天引き額と同額を天引きします。 | 確定した年間保険料額から、仮徴収で納めた額を差し引き、残った額を3回に分けて天引きします。 | ||||
※年金額18万円以上の方でも、次のような場合は一時的に普通徴収となります。
| 普通徴収となる事由 | 内容 |
|---|---|
| (1)所得変更等で保険料段階が変更になり保険料が増額となった | 増額分を納付書で納めていただきます |
(2)年度途中で
| 特別徴収の対象者として把握される月の概ね6か月後から特別徴収が開始となります → それまでは納付書で納めます |
| (3)所得変更等で保険料段階が変更になり保険料が減額となり、当該年度の特別徴収が停止となった | 翌年度の介護保険料のうち半分を納付書で納めます |
【保険料を納めないでいると・・・】
- 介護保険料の納付義務(介護保険法第132条)
被保険者本人に納付義務があることはもちろんですが、その世帯主及び配偶者の一方は、当該保険料を連帯して納付する義務を負うことが規定されています。
特別な事情がないのに、保険料を納めないでいると、介護サービスを受けるときに滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
(1)1年間以上滞納していると・・・(介護保険法第66条)
サービス利用料の全額を一旦利用者が負担しなければならなくなります。
※申請により後から保険給付分(9割、8割又は7割相当分)が払い戻されます。
(2)1年6か月以上滞納していると・・・(介護保険法第67条)
保険給付の一部、または全部が一時的に差止めとなります。
(3)2年以上滞納していると・・・(介護保険法第69条)
滞納期間に応じて、本来1割から3割である利用者負担が3割又は4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。