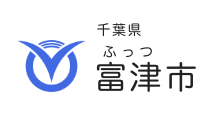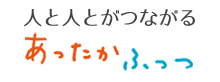現在位置
あしあと
日本遺産候補地域「鋸山」ストーリーと主な構成文化財
- 初版公開日:[2024年03月05日]
- 更新日:[2024年3月5日]
- ID:7892
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ストーリーの概要
東京湾に突き出し富津市と鋸南町にまたがる鋸山。ギザギザとした山の形はまさにノコギリ。
ロープウェーで山頂に向かえば、採石産業により作られた巨大な直壁と大空間の連なりが迫ってくる。山頂の崖っぷちからは身震いするほどスリリングな絶景。南側の斜面には、岩に彫られた壮大な大仏や観音像、洞穴に配された石像群があり、日本寺境内に神秘的な世界を広げる。
日本の近代化を支えた「房州石」の山は、信仰の山として、石切場として、古来より人々を惹きつけ続ける。鋸山は、信仰と産業の歴史が織り成す大自然のミュージアムだ。


ストーリー
地球の恩恵 鋸山のなりたち
東京湾を三浦半島から房総に向かうフェリー。深海1,000mの海上から対岸を望めば、標高329mとは思えぬ迫力の山。
富津市と鋸南町の境にあって、海に突き出すようにそびえる巨大な「ノコギリ」、鋸山。
約500万年前、海底であったこの地は、砂や泥、火山噴出物が沈み固まった地層が隆起して陸地となった。その後、南北からの圧力で波状に変形し、外側の軟らかい部分が風雨で崩れ、中心の硬い部分が残り、鋸の刃のようなギザギザとした山筋が自然の力によってつくられた。

東国の霊山・鋸山
鋸山は古来より信仰の対象であった。南側の斜面にある日本寺は、神亀2年(725)に行基が開いたとされる。聖武天皇の命により東国へ向かった行基は、薬師如来の示す地を目指して霊山・鋸山に辿りつく。古くから峠や川は災いを避ける境界として大切にされており、はやり病や災いから国を救い護るため、安房と上総の国境である鋸山に薬師如来の寺は開かれた。
中世には、石橋山の戦いに敗れた源頼朝が、鋸南町猟島に流れ着く。頼朝伝説はじまりの地である。頼朝は、荒れ果てていた日本寺で武運回復を祈願する。再起を果たした頼朝は、すぐさま日本寺の修工に尽力し、養和元年(1181)薬師本殿を再建した。その後の戦火で再び荒廃するが、足利尊氏により復興されている。戦国時代には、国指定重要文化財である梵鐘も東京湾をわたり鋸山へ辿りつく。霊山・鋸山は度重なる衰退の危機を乗り越えた復興の象徴でもある。
名勝地鋸山の誕生
江戸中期の住職・高雅愚伝は、山の下にあった日本寺を中腹に移転した。山中の奇岩や洞穴に石仏を並べるよう発願し、名工大野甚五郎英令は20年の歳月と生涯をかけ、その数世界一とうたわれる千五百羅漢石像群をつくり上げた。一つとして同じ顔のものはなく、洞穴ごとに物語があり、仏教世界が具現化された空間は、仏教の教えが得られる施設として、江戸近郊から多くの参詣者が訪れた。岩に彫られた壮大な大仏も、この時につくられたものである。
海岸にそびえ立つ絶壁に打ちつける波間を渡る人。日本水仙が咲き乱れ、開けた視界には海越しに富士山が見渡せる。自然豊かな低名山と海のもたらす絶景に、日本寺の神秘的な世界観が加わり、名勝地鋸山が誕生した。数多の文人墨客からも愛される場所となり、俳人・小林一茶、浮世絵師・歌川広重も度々この地を訪れ、鋸山を題目とした。明治期には夏目漱石が学生時代の夏休みをこの地で過ごし、『木屑録』にその様子を書き起こしている。

発達する採石産業
景勝地の人気の高まりとともに、岩を砕くツルハシの音も大きく鳴り響いた。鋸山は「房州石」と呼ばれる凝灰質砂岩で、高さによって石質が異なる。最上級石材の桜目は山頂付近で採掘された。採石技術の発達とともに、人々はしのぎを削って山を登り、質の高い石材を求めて山を削った。江戸から東京へという近代化の大波にのり、鋸山での採石は地域の一大産業として急成長を遂げた。
加工しやすく火に強い房州石は、カマドや七輪、燈籠の他、建築石材としても重用され、横浜港や台場建築、海堡の礎石となった。文字どおり日本の近代化を基礎から支えたのである。
男たちが切り出した石材は、ねこ車と呼ばれる台車に乗せられた。200kgを超す石材を運ぶのは女たちで、急な山道を日に何度も行き来した。
登山道では採石の跡が各所にみられる。ねこ車のブレーキ痕が残る車力道や、石を滑らせた樋道、石材の搬出路であった細い切通しの岩肌に触れれば、当時の石工の様子が想像させられる。
石切場跡に残る巨大な直壁を見上げると、膨大な労力により刻まれた無数のツルハシの跡から、滑らかな岩肌へと変わる高さがある。手掘りから機械化への変化をはっきりと示すこの位置こそ、チェーンソーが導入された昭和33年(1958)当時の石切場の高さだ。それまで石工1人当り1日8から10本であった石材生産量は80から100本と10倍に増え、石を運ぶ作業もワイヤーを張った索道を利用するようになった。


房州石がつくりだす「石と芸術のまち」
採石業は、コンクリートの普及等により昭和60年(1985)に終わりを迎える。しかし、麓の町中には石塀や石蔵が残り、カフェや美術館にも房州石が用いられている。石材の里帰りも行われるなど、今も「石のまち」は健在である。
近年では、この地に滞在した芸術家たちが鋸山をモチーフにした作品で町中を彩り、境内に取り込まれた「地獄のぞき」、「百尺観音」は、かつての石切場跡に新たな魅力を生みだした。反響する立地を活かした岩舞台でのコンサートも好評だ。名勝地鋸山は、浮世絵から現代アート、音楽まで楽しめる「石と芸術のまち」として、さらなる発展を続けている。ロープウェーやフェリーから見上げる鋸山、海岸線をぬって走る電車の車窓からの景色。交通手段や登山ルートを変えると、また違った世界が楽しめる。この景観に魅了された移住者・経営者も増加し、国内外からのイノベーションの口火が、鋸山を中心に切られようとしている。
「春風や 鋸山を砕く音」とうたった正岡子規は、百年後には石の採りすぎで地図から鋸山が消えるかと心配したが、石の切り出しは、旧安房国と上総国の国境である尾根と、信仰の中心である日本寺を避けて行われた。細かな刃のように残された山頂の崖っぷちは、信仰と産業の共存の象徴である。大自然と人々が創りあげた「自然と歴史のミュージアム」、鋸山。古来より幾度も再起を遂げた天空の岩山は、人々を惹きつけ結びつけ、これからも力を与え続ける。